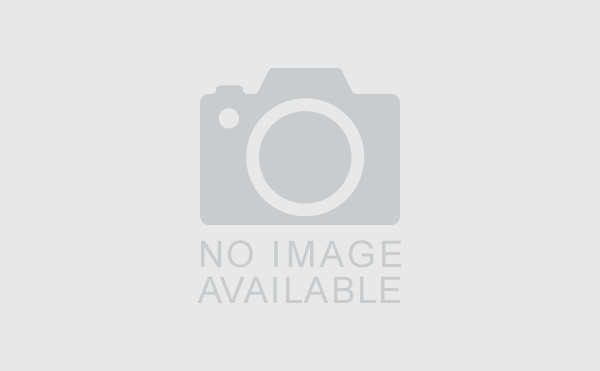再婚家庭で遺言が必要な理由|前妻の子・連れ子との相続トラブルを防ぐには?
目次
- 前妻の子も相続人に|再婚後の財産でも“分け合う”ことになる可能性
- 連れ子には相続権がない|遺さなければ“ゼロ”になる現実
- 相続人同士が“他人”だからこそ、トラブルになりやすい
- 遺言書があればできること|今の家族に確実に遺す方法
- 遺言がなかったことで起きたもう一つの現実|家族のように暮らしてき たのに
- まとめ
再婚して長い年月が経ち、今の家族との暮らしがすっかり日常になっていると、
「相続の準備なんて、まだ先の話」と感じる方も多いかもしれません。
けれど、いざ相続となったとき、
前の結婚で生まれたお子さんや、ご自身の連れ子との関係が、
思いがけないかたちで影響してくることがあります。
「家は夫と2人で築いたのに、前妻の子と分けることに?」
「一緒に暮らしてきた連れ子には、何も遺せない?」
そんな状況を防ぐためには、遺言書を通じて家族への思いをきちんと形にしておくことが大切です。
この記事では、再婚家庭でなぜ遺言書が必要なのかを、実際に起こった事例を交えて分かりやすく解説します。
「うちは大丈夫」と思っている方にこそ、ぜひ読んでいただきたい内容です。
①前妻の子も相続人に|再婚後の財産でも“分け合う”ことになる可能性
再婚後に築いた財産であっても、相続が発生したときには前の配偶者との子どもが相続人になることがあります。
たとえ、今の配偶者と一緒に家を買って長年暮らしていたとしても、法律上は、すべての子どもが同じように相続人とされます。
たとえば、亡くなった方に「前の結婚で生まれた子どもが2人」いて、
現在の配偶者がいる場合、相続分は【配偶者が1/2、子どもたちが1/2(2人で1/4ずつ)】となります。
この場合、自宅などの不動産は共有名義になりやすくなります。
共有名義の不動産を売却して持分を現金化したいという希望が他の相続人から出されることもあり、住み慣れた自宅を手放す事態に発展することも少なくありません。
🔹事例:相続後、自宅を手放すことになったAさんのケース
Aさん(60代の女性)は、20年前に夫と再婚しました。
その後ふたりで中古の一戸建てを購入し、夫婦で支え合って暮らしてきました。
住宅ローンは夫一人で組み、家の名義も夫だけでした。
夫が亡くなったあと、相続人として現れたのは、前妻との間に生まれた子どもたち2人。
法律に従って遺産を分けた結果、自宅はAさんと子どもたちの共有名義になりました。
やがて子どもたちから「家の持ち分をお金にしてほしい」と求められ、
Aさんは住み慣れた家を手放さざるを得ませんでした。
「この家は、夫と私で築いた人生の場所でした。
遺言があれば、もっと違った未来があったかもしれません。」
②連れ子には相続権がない|遺さなければ“ゼロ”になる現実
再婚相手の連れ子とは、法律上の親子関係があるとは限りません。
たとえ日常的に「家族」として接していたとしても、法律上は親子関係がなければ相続権は一切認められないのが現実です。
再婚しただけでは、自動的に親子になるわけではありません。
養子縁組をしていなければ、相続人ではないと扱われるため、
何も手続きしていなければ、連れ子には財産をまったく遺すことができません。
これは、たとえばこんなケースで問題になることがあります。
- 夫が再婚相手の連れ子を実子のようにかわいがっていた
- しかし、養子縁組をしておらず、遺言もないまま亡くなってしまった
- 結果として、その連れ子には一円も相続されなかった
このような場合でも、遺言書があれば「遺贈」という形で財産を残すことが可能です。
たとえば、預金の一部や車、不動産の持分などを「誰に、何を、どれだけ渡すか」を自由に指定できます。
また、連れ子との関係が深く、正式に相続人としたい場合は養子縁組を検討する方法もあります。
ただし、養子縁組をすると他の子どもとの相続分のバランスが変わるため、注意が必要です。
「家族のように暮らしていたのに、相続では“他人”になる」
そんな切ないすれ違いを避けるためにも、早めの備えが大切です。
③相続人同士が“他人”だからこそ、トラブルになりやすい
再婚家庭の相続では、相続人同士が感情的にも距離があることが多いという特徴があります。
前妻との子ども、現在の配偶者、そして場合によっては連れ子——
法律上の立場が異なるうえ、お互いに「親しみ」や「信頼関係」がないまま話し合いをしなければならないこともあります。
そのため、以下のようなトラブルが起こりやすくなります。
- 前妻の子どもが、現在の妻に対して「本来ならすべて自分たちが受け取るはずだった」と不満を持つ
- 現在の配偶者は、「一緒に暮らしてきたのは自分なのに…」と精神的な負担を抱える
- 相続分でもめて話し合いがまとまらず、調停や裁判に発展するケースも
とくに遺産に不動産が含まれている場合は、「分けにくい」「金額の評価が難しい」という理由で、話し合いが長引いたり、こじれたりすることが多くなります。
また、親族間の関係が希薄なため、感情的に対立しやすいという傾向もあります。
「相続人」であっても、「親しい家族」とは限らない。
それが、再婚家庭ならではの相続の難しさです。
こうした問題を避けるためには、やはり遺言書を残しておくことが基本となります。
分け方を明確にすることで、相続人同士が顔を合わせて争うリスクを大きく減らすことができます。
④遺言書があればできること|今の家族に確実に遺す方法
再婚家庭において、相続をめぐるトラブルを未然に防ぐためには、遺言書の作成が最も有効な手段のひとつです。
法律では「誰が法定相続人か」は決まっていますが、「誰に何を遺すか」は遺言書で自由に決めることができます。
遺言書によってできることは、主に以下の3つです。
1. 「誰に、何を、どれだけ」遺すかを明確にできる
遺言書があれば、たとえば以下のような指定が可能です:
- 今の配偶者に「自宅」を遺す
- 前妻の子には**「預金の2分の1のみ」など
- 連れ子に財産の一部を**「遺贈」**する(相続人でなくても可能)
相続人間での話し合い(遺産分割協議)を避け、あらかじめ分け方を決めておくことができます。
ただし、法定相続人には「遺留分(最低限の取り分)」が認められているため、
たとえば前妻の子どもを完全に除外したいと思っても、遺留分を侵害すると争いに発展する可能性があります。
そのため、前妻の子には「遺留分を侵害しない範囲で最低限の金額を指定する」など、無理のない形にしておくことが大切です。
2. 連れ子に財産を遺すこともできる
養子縁組をしていない連れ子には相続権はありませんが、
遺言書によって**「遺贈(特定・包括)」**という形で財産を渡すことが可能です。
- 特定遺贈:○○銀行の預金100万円を○○に
- 包括遺贈:全財産の20%を○○に
3. 感情的なトラブルを避けやすくなる
遺言書の中に「付言事項(ふげんじこう)」を記載しておくことで、
なぜそのように分けたのかという想いや背景を残すこともできます。
たとえば:
「長年支えてくれた妻に安心して暮らしてもらいたい」
「子どもたちには別の形ですでに支援をしてきた」
など、形式的な分け方だけでなく、遺言者が亡くなった後も、人間関係を円満に保つ配慮としても役立ちます。
付言事項があるかないかで、家族が受け取るものだけでなく、心のあり方も変わります。
再婚家庭だからこそ、「遺す人の想いを見える形にする」準備が大切です。
⑤遺言がなかったことで起きたもう一つの現実|家族のように暮らしてきたのに
再婚家庭の相続では、法的な関係の有無が結果を大きく左右します。
とくに「連れ子」は、養子縁組や遺言がなければ法律上の相続人ではないため、
どれだけ身近で暮らしていても、一切の財産を受け取ることができません。
実際に、次のような事例がありました。
🔹事例:面倒を見てきた連れ子に、何も遺らなかったケース
ある男性は、妻とその連れ子と共に長年暮らしていました。
夫婦は仲睦まじく、連れ子も実の子のように接していました。
その家には妻、連れ子、その配偶者、そして孫まで一緒に住んでおり、
家族ぐるみで生活を支え合っていました。
やがて妻が先に亡くなり、その後は連れ子夫婦が男性の生活を支えるようになりました。
買い物や通院の付き添い、介護的なサポートまで行い、
連れ子は最後まで「実の親」として世話をし続けました。
ところが——
男性は遺言書を作らないまま亡くなりました。
養子縁組もされておらず、連れ子には法的な相続権がなかったのです。
その結果、相続人となったのは、前妻との間に生まれた子どもたち。
連れ子家族が長年住んできた家も、預貯金も、すべて前妻の子たちが相続しました。
連れ子には、何ひとつ遺されませんでした。
このような結末は、「相続は気持ちだけでは決まらない」という事実を突きつけます。
もし、遺言書があれば——
「この家は〇〇に残したい」「支えてくれた家族に感謝を伝えたい」という想いを、
法的に実現することができたはずです。
【まとめ】再婚家庭こそ遺言が必要な理由
再婚家庭では、家族の形が一人ひとり違います。
前の配偶者との子どもがいたり、連れ子と生活していたり——
いま目の前にいる「家族」と、法律上の「相続人」とが一致しないことも珍しくありません。
そんな中で、何も準備しないまま相続を迎えてしまえば、
大切な人に財産を残せないどころか、望んでいなかった人にすべてが渡ってしまうこともあり得ます。
遺言書があれば、
- 今の配偶者に自宅を遺す
- 連れ子にも感謝の気持ちを込めて遺贈する
- 前妻の子とのトラブルを未然に防ぐ
といった、「本当に遺したい人」に確実に想いを届ける手段になります。
家族にとって、相続は「お金の問題」であると同時に、「人の関係」にも深く関わるものです。
だからこそ、再婚家庭にとって遺言書は、単なる財産の分け方ではなく、家族を守るための大切な準備といえるのではないでしょうか。
今の家族の安心のために、
そして、将来誰もが納得できる相続のために——
遺言書の作成を、ぜひ一度、真剣に考えてみてください。
📞 無料相談・ご予約はこちらから
👉【お問い合わせフォーム】または【お電話:045-232-4491】
横浜で相続や遺言のご相談なら、経験豊富な行政書士が丁寧に対応いたします。
未来の安心のために。
まずは一歩、踏み出してみませんか?