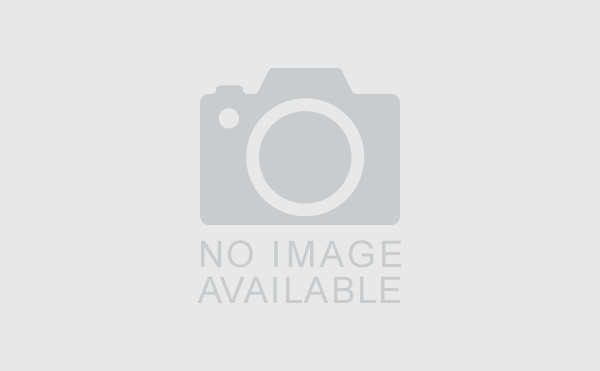生前に相続放棄はできない?|“伝えておきたい想い”は遺言で残す
「子どもには相続放棄してもらいたいのよね」
そんなご相談を受けることがあります。
・遺産をめぐって、兄弟でもめてほしくない
・関わってほしくない相続人がいる
・特定の子に財産を集中的に渡したい
――そんなとき、「今のうちに放棄してもらえたら安心なのに」と思われる方もいらっしゃいます。
けれど、残念ながら相続放棄は生前にすることはできません。
たとえ「放棄します」と言っても、それを法的に約束することはできないのです。
ですが、「できないこと」がある一方で、
「今だからこそできること」もあります。
それが――
あなたの想いを“かたち”にして残すこと。
このページでは、
- なぜ生前に相続放棄ができないのか?
- 「放棄させたい」と思ったとき、どんな備えができるのか?
- 遺言書を使って、意思と想いをきちんと残す方法
を、やさしく解説していきます。
第1章:なぜ生前に相続放棄はできないのか?
「今のうちに、子どもに『相続はいらない』と言ってもらえれば安心できるのに」
そう思うのは自然なことです。
ですが、相続放棄は**“相続が始まってから”でなければできない**と法律で決められています。
民法第915条では、こう定められています:
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、
相続について承認または放棄をしなければならない。
ここでいう「相続の開始」とは、被相続人が亡くなった時のことを指します。
つまり、まだ相続が始まっていない=生きている間には、放棄の手続きそのものができないのです。
なぜ生前の相続放棄はできないの?
理由は主に次の2つです:
① 相続する権利は「亡くなったとき」に初めて発生するから
そもそも、相続権というのは“まだ始まっていない権利”です。
存在していないものを「放棄する」ことはできません。
② 不公平な扱いや強要を防ぐため
仮に生前に放棄できる制度があったら――
親から「あなたは相続しないって書いて」と迫られたり、家族間で不平等が生じたり、
トラブルが起こる可能性も出てきます。
そのため、法律は「放棄するかどうかは、相続が始まってから本人が判断すること」と決めているのです。
じゃあ、“あらかじめ決めておく”ことは全くできないの?
たとえば、「相続放棄します」と家族内で口約束したり、
放棄に関する契約書を作っておくことは可能ですが――
それは法的には一切効力がありません。
「口約束しておいたのに、実際には放棄しなかった」
そんなときも、文句を言うことはできませんし、裁判でも通りません。
まとめ:相続放棄は、生前にはできません。でも……
だからといって、“何もできない”わけではありません。
「この人には渡したくない」
「こう分けたい」
「家族がもめないように、きちんと考えておきたい」――
そんな想いがあるなら、
それをきちんと「残す」方法があるのです。
次章では、
「生前に放棄はできない。でも、できることはある」
その最も現実的で有効な手段――遺言書について、わかりやすくご紹介します。
第2章:相続放棄できないなら、どうする?|遺言で“想い”を伝えるという選択
「放棄させることはできない」と聞くと、
「それならどうしたらいいの?」と不安になりますよね。
けれど実は、相続において一番大切なのは
「放棄させる」ことではなく、
**「誤解を生まないよう、想いと意思をきちんと伝えておくこと」**です。
そして、その想いをきちんと残せる方法が――
遺言書です。
遺言書があれば「どう分けるか」を自分で決められる
遺言書には、財産を誰にどのように渡すかを明記することができます。
たとえば…
- 特定の子どもに不動産を相続させたい
- ある子には遺産を渡さないようにしたい
- 相続人以外の人(長年お世話になった人など)にも渡したい
このようなご自身の意思を、法的に有効な形で残すことができるのが、遺言書の強みです。
「なぜそうしたのか」も伝えられる
さらに、遺言書には「付言事項(ふげんじこう)」といって、
法的効力はないけれど、気持ちや背景を伝える文章を添えることができます。
たとえば──
「〇〇は長年、私と同居し介護をしてくれました。その感謝の気持ちを込めて、不動産は〇〇に遺します。
他の子どもたちも、どうか私の気持ちを理解してくれることを願っています。」
このようなやさしい言葉のひとことがあるかないかで、家族の受け止め方は大きく変わります。
※「付言事項をもっと詳しく知りたい方はこちら」
「放棄させる」より、「納得してもらう」
もし遺言書がなく、法定相続どおりに分けることになった場合、
相続人全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。
話し合いがうまくいかなければ、調停や裁判に発展することも。
でも、遺言書があれば、
基本的には書かれたとおりに分けることができます。
そして、「なぜそうしたか」を丁寧に伝えることで、
たとえすべてに納得されなかったとしても、あなたの気持ちはきっと届きます。
まとめ:想いをかたちにする「遺言書」が、あなたと家族を守る
「放棄してくれれば安心」
そう思う背景には、
家族がもめないようにしたい、余計な苦労をかけたくない――という親の優しさがあるはずです。
その優しさこそ、
遺言という“かたち”にして残すことができるのです。
次章では、他にも「できること」として知られている対策を簡単にご紹介した上で、
なぜやはり遺言がもっとも現実的で安心な手段なのかをご説明します。
第3章:他にもできることはあるけれど…やはり“遺言”が安心な理由
「相続放棄ができないなら、何か他に方法はないの?」
そう思われる方も多いでしょう。
確かに、相続対策として“できること”はいくつか存在します。
でも、それぞれに制限やリスクがあり、遺言ほど確実で柔軟な手段はありません。
ここでは、代表的な方法を簡単にご紹介しながら、
なぜ“遺言”がもっとも安心できる手段なのかをお伝えします。
1. 生前贈与
「生きているうちに財産を贈っておけば、相続では揉めないのでは?」
と思われがちですが、実は注意点が多い方法です。
- 贈与税の負担が大きくなる可能性がある
- 他の相続人から「不公平だ」と不満が出ることも
- 死後に「特別受益」として持ち戻され、結局トラブルになることもある
生前贈与は計画的に行えば有効な手段ですが、
“公平感”の調整が難しく、相続トラブルの火種になることもあります。
2. 遺留分の放棄(家庭裁判所への手続きが必要)
相続人に対し「遺産はいらない」と事前に確約してもらうための手段として、
「遺留分放棄」という方法もあります。
ただし、これは家庭裁判所に申し立て、許可を得なければできません。
しかも、本人の自由意思でないと認められず、簡単に使える制度ではないのが実情です。
3. 推定相続人の廃除(かなり限定的)
「絶対に財産を相続させたくない」
という場合、相続人の廃除という制度もあります。
ただしこれは――
- 暴力や重大な非行など、家庭裁判所が認める“やむを得ない事由”が必要
- 非常にハードルが高く、一般的な家庭では現実的でない
という点から、使えるケースはごく限られています。
やはり、遺言がいちばん自然で、穏やかで、確実
これらの方法と比べても、やはり遺言がもっとも柔軟で、確実です。
- 誰に、どの財産を、どのように残すかを明記できる
- 遺留分に配慮しつつも、あなたの意思を明確に反映できる
- 「なぜそうしたのか」も、付言でやさしく伝えられる
あなたの気持ちと、家族への思いやりを、
“穏やかに”“法的に”“確実に”残すことができるのが遺言です。
まとめ:遺言は、家族への最後の手紙
他の方法では代替しきれない“思いの伝え方”が、遺言にはあります。
相続は「お金の問題」だけではなく、「感情の問題」「家族関係の問題」でもあります。
だからこそ――
あなたの言葉で、あなたの手で、大切な人たちへの想いを伝える。
それができるのが遺言書であり、
それこそが、あなたの残せる“最高の相続対策”です。
第4章:遺言が“ある家”と“ない家”、どう違う?
「相続放棄は生前にはできない」と聞いて、
「じゃあ、今のうちに何ができるの?」と思った方も多いのではないでしょうか。
その答えは――
“想いを伝える遺言を作っておくこと” です。
遺言は、「放棄してほしい」「相続しないでほしい」といった生前の希望を、
法的に・現実的に叶えられる、ただ一つの手段とも言えます。
実際に、遺言があったことでスムーズに相続が進んだご家庭もあれば、
遺言がなかったために思わぬトラブルに発展したご家庭もあります。
ここでは、「備えた人」と「備えなかった人」で、何が違ったのか。
実際の事例を通して見ていきましょう。
ケース1:家を長女に残したら、他の兄弟が猛反発…
【背景】
母親と長女が長年同居し、母の介護を献身的に行ってきました。
母は「家は長女に」と希望していましたが、遺言書は残さずに他界。
【結果】
他の兄弟は「公平じゃない」と主張し、遺産分割協議が大揉めに。
話し合いは長期化し、兄弟同士の関係は完全に断絶してしまいました。
【もし遺言があったら…】
「家は長女に」「理由は、今までの感謝とこれからの生活のため」
そんな一言があれば、納得とはいかずとも、受け入れる材料になったはずです。
ケース2:財産はほぼ預金。でも遺言がなかったばかりに…
【背景】
父の財産は、ほぼ預貯金。法定相続どおりに分ければよい…と思いきや、
一部の兄弟が「親の介護をしていたのに、割に合わない」と反発。
【結果】
「使途不明金がある」「勝手に引き出していた」などの争いに発展。
家庭裁判所に持ち込まれるまでに至りました。
【もし遺言があったら…】
「預金は均等に分ける」「ただし、○○には生前の感謝をこめて100万円を追加で…」
など、わずかな工夫でトラブルは回避できたはずです。
ケース3:子のいない夫婦。妻の兄弟が登場して…
【背景】
子どものいない夫婦で、夫が他界。
遺言書がなかったため、妻と夫の兄弟が相続人に。
【結果】
「兄弟が遺産分割に応じてくれず、家の名義変更ができない」
「亡き夫の実家と疎遠なのに、何度も連絡を取らなければならない」
妻の精神的ストレスは相当なものでした。
【もし遺言があったら…】
「すべて妻に相続させる」と一筆書いてあれば、
妻の生活も、気持ちも、ずっと守られていたことでしょう。
「遺言があったら…」という後悔を、これ以上増やさないために
ご家族にとって、遺言は「遺産の分け方」以上の意味を持ちます。
それは、あなたの想いを伝えるもの。
そして、残された人が前に進むための“道しるべ”です。
「そのうち考えよう」と思っていても、
突然の病気や事故で間に合わないこともあります。
いま、元気なうちに――。
それが、あなた自身にとっても、ご家族にとっても、いちばん安心できる選択です。
※「前妻との子がいる場合など、複雑な家族関係の方はこちらの記事もおすすめです」
👉 再婚家庭で遺言が必要な理由|前妻の子・連れ子との相続トラブルを防ぐには?
第5章:想いを遺す“遺言書”のすすめ
「生前に相続放棄はできない」――
これは法律上の決まりです。
けれど、それだけを聞くと「じゃあ、何もできないの?」と不安になる方もいるかもしれません。
確かに、生きているうちに相続人に「あなたは相続を放棄してください」と言っても、法的にその約束は意味を持ちません。
ですが、“遺言書”には、それに代わる力があります。
たとえば――
「この財産は、●●に託したい」
「家族がもめないよう、きちんと分け方を決めておきたい」
「自分の気持ちを、ちゃんと伝えておきたい」
そんな想いを、法的に有効なかたちで残せるのが、遺言書なのです。
特に、公正証書遺言にしておけば、残されたご家族にとっても安心材料になります。
手続きがスムーズになり、争いや迷いを防ぐ効果も大きいからです。
また、第3章でご紹介したように、「付言事項」を添えることで、ただの“お金やモノの分け方”ではなく、“あなたらしい想い”をしっかり伝えることができます。
実際に、これまで私が関わったご家庭でも、付言の言葉によって
「気持ちが分かったから、受け入れられた」
「“なぜそうしたのか”が伝わって、心が穏やかになった」
というお声をいただくことは少なくありません。
遺言は、未来への準備であると同時に、
“大切な人たちへ贈る最後の手紙”でもあります。
だからこそ、相続を“争族”にしないためにも、
「今できること」として、遺言書の作成を真剣に考えてみてほしいのです。
まとめ:いちばん大切なものは、“あなたの想い”です
「生前に相続放棄はできない」
この法律の壁に直面したとき、何より大切になるのは「あなたの意思を、どう残すか」です。
相続には、財産の分け方を超えた“気持ち”が関わります。
「誰に、どんな思いで残したいか」
「争わずに、感謝して受け取ってほしい」
そうした願いは、書き残さなければ伝わりません。
私は、遺言のご相談をお受けする際、必ず「付言事項」を添えるよう強くおすすめしています。
ときに、法的な本文よりも、付言に書かれた言葉がご家族の心を動かし、納得へと導いてくれることがあるからです。
遺言は、あなたの財産と、あなたの人生の「締めくくりのメッセージ」。
「こんなふうに生きて、こんなふうに家族を想っていた」
その想いが伝われば、残された人たちもまた、前を向く力を得られます。
相続を「もめごと」にしないために。
そして、あなたの想いをきちんと届けるために――
遺言書を、前向きな準備として考えてみませんか?
遺言書のこと、気軽にご相談ください
遺言は、法律的なルールだけでなく、あなたの“想い”をどう形にするかが大切です。
だからこそ、形式だけではない、気持ちに寄り添ったサポートが必要だと私は考えています。
「何から始めたらいいのかわからない」
「どんな内容にすれば家族が納得してくれるか不安」
――そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください。
お一人おひとりの状況に合わせて、
法律と気持ち、両方の側面からサポートいたします。
無料相談・ご予約はこちらから
【お問い合わせフォーム】または【お電話:045-232-4491】
横浜で相続や遺言のご相談なら、経験豊富な行政書士が丁寧に対応いたします。
未来の安心のために。
まずは一歩、踏み出してみませんか?