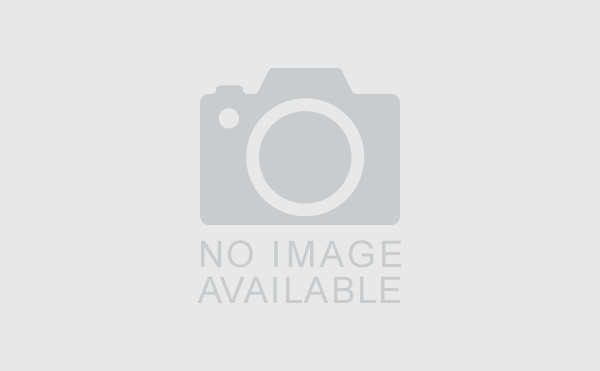付言事項とは?|遺言書に“想い”を残して争族を防ぐ方法
「うちは家族仲がいいから、遺言なんていらないよ」
そう思っていたのに、お父さんが亡くなったあと、子どもたちの関係がぎくしゃくしてしまった……。
実は、そんなケースが少なくありません。
法律上の遺言書は「財産をどう分けるか」を決めるものですが、
それだけでは、あなたの大切な気持ちまでは、家族に届かないかもしれません。
だからこそ、**家族への“想い”を言葉にして伝える「付言事項(ふげんじこう)」**が、大切になります。
このページでは、
- 付言事項とは何か?
- なぜ書くことが争い防止につながるのか?
- 実際にどんなことを書けばいいのか?
を分かりやすく解説していきます。
第1章:付言事項とは?(行政書士を自然に入れたバージョン)
付言事項とは、遺言書にそっと添える、あなたの想いや家族への気持ちを伝えるための言葉です。
法律では決められないような、あなたの想い、大切にしてきた気持ちを伝えることができるのが、この付言事項です。
たとえば──
- 財産を多くもらう子どもと、少ない子どもがいるとき
- 特定の人にだけ遺産を残すとき
- 子どもがいないご夫婦で、配偶者に全てを残すとき
このような場合、何も説明がないと、残された家族が不信感を抱き、争いに発展することもあります。
ですが、付言事項で
「〇〇は長年同居し、介護をしてくれました。その感謝の気持ちを込めて、多めに残します」
といった言葉があるだけで、受け取る側の納得感が大きく変わるのです。
付言事項は、
- 自筆証書遺言でも、公正証書遺言でも記載が可能
- 形式にとらわれず、自分の言葉で気持ちを伝えられる
という点で、**気持ちと法律をつなぐ大切な“架け橋”**になります。
何を書いたらいいか迷ったときは、遠慮なく相談してください。
言葉にするお手伝いをするのも、私たちの役目ですから。
実際に、公正証書遺言を作るときには、「こんなことを書いてもいいですか?」とご相談くださる方が多く、一緒に言葉を整えながら、想いのこもった遺言を仕上げています。
第2章:なぜ付言事項が重要なのか|実際のトラブル例をもとに
遺言書は、法律に従って「誰に、どれだけ財産を渡すか」を決めるための書類です。
けれど、それだけでは残された家族が“納得できる”とは限りません。
特に、相続の割合に差がある場合や、一部の相続人を外すような内容の場合は、
「なぜ自分は少ないのか」「どうして私には遺さないのか」と、不満や誤解が生まれやすくなるのです。
●実際にあったケース①
長男と二男に、父親の遺産を不平等に分けた遺言。
内容は「長男に8割、次男に2割」でした。
二男は「なぜ自分は少ないのか」と納得できず、長男に対して不信感を募らせました。
遺言自体は法的に有効だったものの、兄弟の関係はこの相続を機に絶たれてしまいました。
→ もしここに、「長男は長年父の会社を手伝っていたため、その貢献を考慮した」といった付言があれば、
少なくとも「父はどう思っていたか」を知ることで、次男の感じ方も変わっていたかもしれません。
●実際にあったケース②
再婚した夫が、遺言で「すべてを今の妻に相続させる」と記載。
しかし、前妻との子どもが法定相続人だったため、遺留分を請求してきました。
このとき、妻は「なぜ全部私に遺すと言っていたのか」について説明することができず、
子どもとの交渉が難航。家庭裁判所での調停にまで発展しました。
→ このケースでも、「介護や看病を支えてくれた今の妻に全てを託したい」という付言があれば、
少なくとも妻自身がその言葉を力にして、胸を張って話すことができたかもしれません。
財産は「分ける」ものですが、気持ちは「伝える」ものです。
どんなに公平な分け方をしても、そこにあなたの“想い”が添えられていなければ、家族の心には届かないこともあります。
だからこそ、付言事項は、遺言を“最後の手紙”として仕上げる大切な役割を果たします。 ただの財産の分配ではなく、あなたの本当の気持ち――感謝や願い、家族への祈りを言葉にして残すこと。
それが、残された家族に安心とつながりを届ける、いちばんの相続対策になるのです。
第3章:実際に書かれた付言事項の例
●家族への感謝を伝える例
「これまでの人生、皆のおかげで幸せでした。
つらいこともありましたが、家族の笑顔に何度も救われました。
最後に、心からのありがとうを伝えます。」
家族への想いを、遺言という形で正式に残す機会は、人生で一度きりかもしれません。
「ありがとう」の一言が、どんな相続対策よりも家族の心を支えてくれることがあります。
●相続の分け方に理由を添える例
「〇〇(長女)は、私の晩年を支えてくれました。
その感謝の気持ちとして、他の兄弟よりも多くの財産を渡します。
他の皆にも感謝しています。どうか理解してもらえると嬉しいです。」
遺産の分け方に差があるときは、その理由を伝えることが、誤解や不満を防ぐカギになります。
●争いを避けたいという想いを伝える例
「この遺言は、皆が将来も仲良く過ごせるようにという願いから書きました。
どうか争うことなく、それぞれの人生を大切に歩んでください。」
「親の思いがこうだった」と知るだけで、
子どもたちは“争ってはいけない”という気持ちになりやすくなります。
●配偶者への想いを伝える例
「長年、共に歩んでくれた〇〇へ。
あなたの存在が、私の人生にどれほどの安心と喜びをもたらしてくれたか、言葉では表せません。
心から、ありがとう。」
子どもがいないご夫婦や、再婚家庭では、夫婦間の気持ちを残す付言がとても大切になります。
財産のことだけでなく、人生のパートナーとしての感謝を伝える場でもあるのです。
付言例①(妻への感謝)
私の亡き後、〇〇(妻)が一人になっても、介護や生活に困らないよう、
預金はすべて妻に遺すこととします。
これまで支えてくれた妻への感謝の気持ちです。
◎◎、△△も、どうか私のこの思いを理解して、受け入れてください。
付言例②:長女への感謝と家の相続理由について
長女〇〇は、妻が亡くなった後も私と同居し、日々の生活や介護を支えてくれました。その感謝と、今後も安心して暮らしてもらうために、私の自宅は長女に相続させます。
他の子どもたちも、それぞれにたくさんの思い出と絆があります。
この分け方が、みんなにとって納得のいくものであることを心から願っています。
第4章:付言を書くときの注意点|“想い”が伝わるために
付言事項は、法的効力はないものの、家族への「最後のメッセージ」として非常に重要な役割を果たします。
しかし、書き方を誤ると、かえって争いや誤解を生む原因にもなりかねません。
ここでは、付言を書く際に注意しておきたいポイントを整理しておきます。
① 感情的になりすぎないこと
たとえば「〇〇には世話にならなかった」「△△は冷たかった」など、
他の家族を否定するような表現は避けましょう。
一方を褒めることは良くても、他方を責めると、読んだ人の心に傷を残してしまいます。
② 抽象的すぎない
「感謝しています」「お世話になりました」だけでは、なぜそのような遺産の分け方にしたのかが伝わりません。
具体的な出来事や背景(例:介護・同居・看病など)を添えることで、納得感が生まれます。
③ 長くなりすぎない
伝えたいことが多くても、あまりに長いと、読む側が負担に感じたり、
本来の遺言内容が埋もれてしまうこともあります。
2~5行程度を目安に、要点をしぼって簡潔に書くと良いでしょう。
④ 法的な内容と混同しない
付言事項は、あくまで「想い」を伝えるための補足です。
財産の分け方など法的効力を持たせたい内容は、主文に明確に記載する必要があります。
たとえば「〇〇に家をあげたい」という内容を付言だけに書いた場合、
それだけでは法的に効力が認められないこともあります。
→ そのため、主文で「誰に何を相続させるか」を明確に記載し、
付言ではその理由や想いを伝えるという使い分けが大切です。
⑤ 公正証書遺言を作成する場合は、付言希望を伝える
公正証書遺言を作る際も、「付言を入れたい」と公証人や専門家に伝えれば対応してもらえます。
気持ちの部分こそ、プロと相談しながら丁寧に整えることで、想いが正しく伝わることで、“残された人にとって優しい遺言”になるのです。
第5章:まとめ|“想い”を残す付言は、何よりの相続対策
相続でもめる原因の多くは、「金額の多少」ではなく、「気持ちが伝わっていないこと」です。
遺言書の主文が法律に基づいた“ルール”だとすれば、
付言事項は、家族の心をつなぐ“メッセージ”のようなものです。
実際に、私は行政書士として遺言書をお預かりするとき、
必ず「付言も入れましょう」と強くおすすめしています。
なぜなら、感情の問題こそが、争いの火種になることをこれまで何度も見てきたからです。
時には、法的な本文よりも、
「お母さん(お父さん)はこう思っていたんだ」と伝わるたった数行の付言が、家族の心を救うこともあるのです。
法的に正しい遺言だけでなく、
“伝える気持ち”が添えられた遺言こそが、あなたの想いをしっかり残せる方法です。
どうか、遺言書を作成される際は、
ご自身の言葉で、最後のメッセージを添えることもご検討ください。
無料相談・ご予約はこちらから
【お問い合わせフォーム】または【お電話:045-232-4491】
横浜で相続や遺言のご相談なら、経験豊富な行政書士が丁寧に対応いたします。
未来の安心のために。
まずは一歩、踏み出してみませんか?