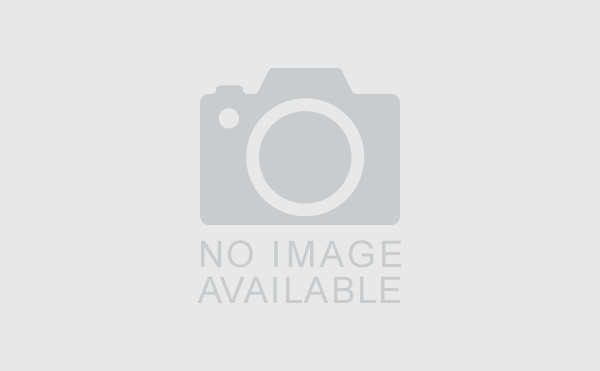死後の手続き、誰に頼む?|今できる備え
亡くなったあと、私のことは誰がしてくれるのかしら?
そんな不安を、ふと感じたことはありませんか?
火葬や役所への届出、家の片づけや支払いの整理——
人が亡くなると、実はたくさんの「手続き」が残されます。
でも、子どもがいない。親族は遠い。頼れる人がいない。
そんなとき、自分の死後を誰に託せばいいのか、不安になりますよね。
そこで注目されているのが、「死後事務委任契約」という制度です。
このブログでは、
亡くなったあとの心配ごとを生前に備える方法として、
死後事務委任契約のしくみやメリットを、やさしく解説していきます。
第1章|「死んだあとが心配」—その理由とは?
「いざというとき、誰に頼めばいいのか分からない」
そう感じている方は、決して少なくありません。
とくに、子どもがいない方、ご夫婦だけのご家庭、配偶者に先立たれた方にとって、
亡くなったあとの“身のまわりのこと”は、大きな気がかりなことのひとつです。
1人暮らしだと、何が起きる?
人が亡くなると、次のような事務的な処理が必要になります。
- 役所への死亡届や火葬許可の申請
- 病院や施設での遺体引き取り
- 葬儀や埋葬の手配
- 自宅や施設の片づけ、遺品の整理
- 家賃や光熱費、保険料などの解約・支払い手続き
- クレジットカード・携帯電話・年金の手続き
こうした“死後の手続き”は、誰かが代わりにやらなければ進みません。
しかし、家族や親族に頼れない場合、手続きが宙に浮いたまま放置されることもあるのです。
実際にあった、困ったケース
- 亡くなったあと、荷物が片づかずにそのまま残されてしまい、施設の管理者や大家さんが対応に追われた。
- 電気・ガス・水道などのライフラインが解約されないまま、使用されていないのに基本料金が引き落とされ続けていた。
- 生前に「知らせてほしい」と言っていた知人や親しい関係者に、亡くなったことを伝えられずに時間が過ぎてしまった。
- 病院で亡くなったあと、ご遺体を引き取る人がいないまま数日が過ぎ、最終的には役所が対応。
こうしたトラブルは、全国で現実に起きています。
「死後のこと」も、“自分ごと”として備える時代へ
生きているうちに準備をしておくことで、
後のことへの不安を、今のうちに和らげることができます。
第2章|「死後事務委任契約」とは?基本とできること
「亡くなったあとの手続きを、誰かにお願いできたら…」
そう思ったときに知っておいてほしいのが、「死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)」という民法上の委任契約です。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、 自分が亡くなったあとに必要となる手続きや事務作業を、あらかじめ特定の人に“お願いしておく”契約のことです。
契約は、生きているうちに結びます。
亡くなったあとは、その契約に基づいて、受任者(引き受けてくれる人)が動いてくれます。
つまり、「自分の死後、誰に、何を、どのように頼むか」を、生前に明確にしておく仕組みです。
どんなことを頼めるの?
死後事務委任契約でお願いできる内容は、以下のようなものがあります。
- 死亡届や火葬許可申請など、役所への手続き
- 病院や施設での遺体の引き取り、火葬・埋葬の手配
- 葬儀・納骨の手配(宗教・宗派・予算の希望も指定できます)
- 賃貸住宅の退去手続き・家財の整理や処分
- 公共料金等未払い金の支払いと精算(内容による)
- 関係者への連絡(友人、勤務先、介護関係者など)
これらは法的に遺言では対応できない部分も多く、
「死後事務委任契約だからこそ、頼めること」がたくさんあります。
● 遺言書や後見制度との違い
ここで混同されやすいのが、遺言書や後見制度との違いです。簡単に整理しておきましょう。
| 制度名 | 内容 | 主な役割 | 対応できるタイミング |
| 遺言書 | 財産の分け方などの指示 | 相続・遺贈 | 死後(財産に関すること) |
| 成年後見制度 | 判断能力が低下したときの支援 | 財産管理・契約行為 | 生前(判断力がなくなってから) |
| 死後事務委任契約 | 死後の事務手続きの委任 | 葬儀・手続き・家財処分など | 死後(生活面の事務) |
つまり、
- 財産に関することは「遺言書」
- 判断能力が不安なときは「後見制度」
- 生活面の事務を死後に任せるなら「死後事務委任契約」
と、それぞれ目的が異なります。
法律に基づいた、きちんとした契約です
この契約は、民法に基づいた委任契約として 公証役場で公正証書として作成することもできます。
内容が複雑な場合や、ご自身での手続きが不安なときは、行政書士や弁護士などの専門家に相談すると安心です。
「口約束では不安」「家族にも頼れない」と感じる方にとって、
死後のことを“法律に基づいて安心して託せる”手段として、非常に有効な方法といえます。
このように、死後事務委任契約は、
「家族がいないから」「子どもに迷惑をかけたくないから」——
そんな思いを持つ方にこそ、知っておいていただきたい制度です。
人生の最期まで、自分らしく安心して過ごすために。
死後の手続きを誰かにきちんと託しておくことは、残される人にとっても、あなた自身にとっても、大切な“思いやり”のひとつになるのです。
第3章|契約しておくと、何が安心か?
「まだ元気だけど、もしものことを考えると心配で…」
そんな声をよく耳にします。
死後事務委任契約は、ご本人が元気なうちに「死後の不安」を整理し、安心を得るための備えです。
ここでは、この契約をしておくことで得られる「安心」とは何か、
そして、生前の気持ちの余裕がどのように変わるのかを、わかりやすくお伝えします。
誰に何を頼むかが「はっきり決まっている」という安心感
もしものとき、自分が亡くなったあとに…
- 誰が火葬をしてくれるのか?
- 家の片づけはどうなるのか?
- 公共料金や入院費の支払いは?
これらがすべて宙ぶらりんのままでは、不安が膨らむばかりです。
しかし、死後事務委任契約を結んでおけば、
「この人が、こういう内容をきちんとやってくれる」という仕組みが整います。
それだけで、落ち着いた気持ちで最期を迎えられるようになります。
信頼できる人に、希望を託せる
この契約では、どんな人に、どんなことを頼むのか、自分で決めることができます。
たとえば──
- 葬儀は質素にしてほしい
- お墓ではなく、樹木葬にしてほしい
- 特定の人だけに連絡してほしい
- 自宅の家財は〇〇に処分してほしい
そうした希望も、契約書の中で伝えておくことが可能です。
つまり、「私らしく最後を迎えたい」という思いを、具体的な形にしておけるのです。
生きている“今”を、穏やかに過ごせる
人は、不安があると、人は心の奥でずっと力が入ってしまうものです。でも、死後のことをきちんと整理し、信頼できる人に託せる状態になっていると、
「あとは安心して日々を過ごそう」という気持ちになれるものです。
特におひとり様・おふたり様の場合、
“何かあったときのこと”がいつも心の片隅にある方も少なくありません。
死後事務委任契約は、そんな不安を和らげ、
「自分らしく今を生きること」を支えてくれる制度でもあるのです。
死後の手続きを誰かにお願いすることは、
「亡くなったあとの準備」というだけでなく、
前向きに今を生きるためのひとつの方法として、
ぜひ覚えておいていただきたいと思います。
第4章|どんな人に必要?実際のご相談例
「死後事務委任契約って、特別な人がするものじゃないの?」
「私のような普通の暮らしでも、必要なのかしら…」
そう思われる方も多いかもしれません。
でも実際には、家族構成や人間関係が変化している現代社会において、多くの方にとって現実的な備えになっています。
ここでは、実際のご相談例をもとに、どのような方に必要とされているのかを見ていきましょう。
兄弟や親族に頼れない「おひとり様」のケース
【ケース1】
70代・女性・未婚・兄弟は遠方
「これまで一人で自由に生きてきましたが、そろそろ自分の最後のことも考えようと思って…」
この方は、兄弟がいるものの高齢で、数年に一度会う程度。頼るのも気が引けるとのことでした。
自宅は賃貸で、身の回りの整理や解約手続きを誰にお願いするかが心配に。
死後事務委任契約で信頼できる第三者に依頼することで、「最後まで自立して生きられる」安心感を持たれました。
配偶者が先に亡くなり「おふたり様」から一人になったケース
【ケース2】
80代・男性・妻に先立たれたあと一人暮らし
「これまでは何でも妻と一緒に考えていたけど、いなくなってから急に“終活”が現実味を帯びてきて…」
この方は、子どもがおらず、夫婦二人で静かに暮らしてこられたタイプ。
今後、自分に何かあったときに、遺体の引き取りや葬儀の手配を誰がやってくれるのかが不安になり、死後事務委任契約を検討されました。
「これで残された手続きの心配がなくなった」と、安心した表情が印象的でした。
子どもはいるけれど「頼りたくない・頼れない」ケース
【ケース3】
70代・女性・離れて暮らす息子あり
「息子はいますが、海外赴任だし、こういうことを頼める関係でもなくて…」
最近は、「子どもがいるから大丈夫」という時代ではなくなってきています。
物理的に遠方に住んでいたり、価値観が合わなかったり、事情があって疎遠になっていたりと、「頼れない理由」は人それぞれです。
この方は、「最後くらいは自分で責任を持ちたい」という想いで契約を検討され、
葬儀や家財整理などの事務手続きを、お任せいただく形をとりました。
「今は元気。でも迷惑をかけたくない」方にも
死後事務委任契約は、「何かあってから考える」ものではなく、
「まだ元気なうちだからこそ備えられる契約」です。
誰かに迷惑をかけたくない。
自分の死後のことも、自分で準備しておきたい。
そんな想いを持っている方こそ、この制度がぴったりです。
これらの事例は特別なケースではなく、
「自分らしく最期まで生きたい」と願うごく普通の方々のご相談です。
「もしかして、私も…」と感じた方は、
一度、ご自身の身のまわりを見つめなおしてみることをおすすめします。
第5章|死後事務委任契約の作成の流れ
「契約しておくと安心なのは分かったけど、どうやって進めればいいの?」
この章では、死後事務委任契約を実際に結ぶまでの流れを、わかりやすくご説明します。
初めての方でも無理なく理解できるよう、順を追って確認していきましょう。
STEP1|誰に任せるかを考える
まず最初に考えるべきは、「自分の死後を誰に託すか」です。
死後事務委任契約は、受任者(お願いする相手)と信頼関係を築くことが非常に大切です。
そのため、誰にお願いするかを慎重に検討する必要があります。
【任せる相手として多い例】
- お世話になっている士業(行政書士・弁護士など)
→ 法律や手続きに詳しく、第三者として客観的に対応してもらえる安心感があります。 - 信頼できる知人・友人
- 死後事務を専門に引き受けてくれる法人・団体
とくに高齢者の方の場合は、士業や専門団体に依頼するケースが増えており、
「家族に頼れない」「親族に迷惑をかけたくない」といった想いから、
第三者へ託す選択肢が一般的になりつつあります。
【年齢の注意点】
契約自体は、成年であれば誰でも受任者になることが可能です。
しかし、現実的には「年齢差」も大切なポイントです。
たとえば、ご自身が70代で、信頼できる方が同年代や少し年上だった場合、
実際に契約を実行する時期には、相手も高齢となり、対応が難しくなっているケースもあります。
そのため、
- できれば10歳以上年下の相手を選ぶ
- 長く関係を維持できる相手かどうかを見極める
- 万が一に備えて、法人や専門家との契約も視野に入れる
といった視点を持つことが大切です。
契約の相手を「信頼できる人だから」と安易に決めてしまうのではなく、
“現実に実行できる相手かどうか”を冷静に考えて選ぶことが、後悔しないための第一歩です。
STEP2|頼みたい内容を整理する
次に、実際にお願いしたい内容を整理しておきましょう。
例:
- 火葬や納骨の希望(場所・方法など)
- 葬儀の形式(宗教・無宗教・費用の上限など)
- 家財の片づけ、住まいの退去手続き
- 公共料金や入院費の支払い
- 親しい人への連絡や通知先
ノートやメモにまとめておくと、契約時にスムーズです。
STEP3|契約書の作成(公正証書にする?)
内容がまとまったら、実際に契約書を作成します。
契約は民法に基づく「委任契約」ですが、トラブル防止のため、書面化をお勧めします。
さらに、より確実にしたい場合は、公証役場で「公正証書」にすることをおすすめします。
【公正証書にするメリット】
- 証明力が高く、後日もめにくい
- 内容が明確で、実行しやすい
- 原本が公証役場に保管され、紛失の心配がない
ただし、公正証書にする場合には本人確認書類や必要な資料の準備が必要です。
STEP4|必要書類の準備
契約にあたっては、以下のような書類を準備します。
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・健康保険証など)
- 認印(公正証書の場合は実印+印鑑証明書が必要になることも)
- 契約内容のメモや希望事項(任意)
もしもご自身での準備に不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談すれば、文案の作成や手続きの代行も対応してもらえます。
STEP5|費用の目安と注意点
死後事務委任契約にかかる費用は、内容や方式によって異なりますが、以下が一般的な目安です。
【費用の目安】
| 内容 | 相場 |
| 契約書作成(書面のみ) | 3~5万円前後 |
| 公正証書作成費用 | 公証人手数料(内容による) |
| 専門家への依頼 | 書類作成+立会いで5~10万円程度(※業務範囲により異なる) |
また、死後の事務にかかる費用(火葬・片づけなど)も、別途準備しておく必要があります。
「死後事務費用預託契約」や「負担付死因贈与契約」などと併用されるケースもあります。
注意点:実行されないリスクを避けるには?
せっかく契約をしても、契約書が見つからなかったり、誰も把握していなかったりすると、実行されないリスクもあります。
そのため、
- 受任者との連絡を密にしておく
- 契約書の写しを信頼できる人に預ける
- 財産の一部を死後の事務費用として明確にしておく
といった準備も大切です。
難しい手続きのように感じるかもしれませんが、
一つひとつ準備をすれば、きちんと整えられる制度です。
不安なときは、行政書士などの専門家に相談してみることも、心強い一歩になります。
第6章|「あなたの死後」を任せる準備を、今から始めるために
「死んだあとのことなんて、まだ先の話」
“まだ早い”と思っていたことも、ふと現実味を帯びる瞬間があるかもしれません。
死後事務委任契約は、決して特別な人だけのものではありません。
自分の最後を自分らしく整えておきたいと願う、すべての人のための制度です。
何から始めたらいい?
「いきなり契約はちょっと…」という方も多いでしょう。
まずは、以下のようなことから始めてみてください。
- 自分が亡くなったあとに、どんなことが気がかりかを書き出してみる
- お願いしたい相手はいるか、いない場合は誰に相談すべきかを考える
- 葬儀や納骨の方法、家財整理など、希望がある部分は整理してみる
- 終活ノートやメモ帳に、気になることを思いついたときに少しずつ書き留める
準備というのは、何も一度に完璧に整える必要はありません。
「まずは考え始めること」が、何よりも大切です。
専門家への相談は、早めが安心
行政書士や弁護士など、終活や死後事務に詳しい専門家に相談することで、
「自分の場合はどうすればよいのか」が明確になります。
- どこまで契約に入れられるのか
- 公正証書にした方がいいか
- 死後事務費用の準備方法
- 他に必要な手続きとのバランス
など、一人で悩むよりも、状況に応じたアドバイスが得られるのは大きなメリットです。
あなたの意思を、あなたの言葉で残せる時代に
誰かに迷惑をかけたくない
最後まで、自分で人生を整えたい
安心して今を生きたい
その願いを叶えるための手段として、死後事務委任契約があります。
あなたの「こうしてほしい」という気持ちを、きちんと伝え、託すことができる時代です。
“そのとき”が来てからでは遅いからこそ、
「今、元気なうちに」準備を始めておくことが、未来のあなたと、周囲の人を守ることにつながります。
終活は、人生の終わりの準備ではなく、
**これからの時間を、安心して過ごすための「贈りもの」**です。
あなた自身のために、そして大切な人のために。
今日から少しずつ、はじめてみませんか?
「死後のことを相談するのはちょっと…」と迷っている方も、まずはお気軽にご相談ください。
横浜を中心に、高齢の方の終活や死後の備えを丁寧にサポートしています。
【お問い合わせフォーム】または【お電話:045-232-4491】