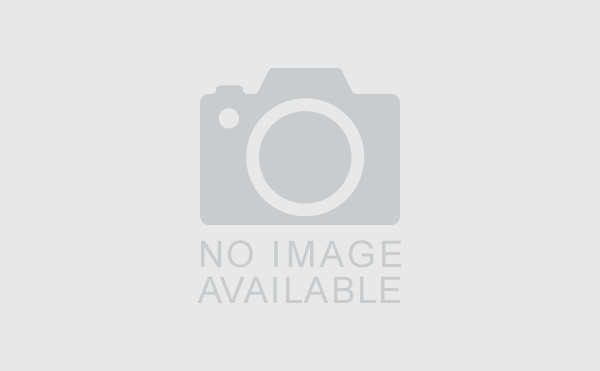遺言書に預貯金額は書かない方がいい?安全な書き方を解説
第1章:遺言書に預貯金額を書くと起こりやすいトラブル
「銀行の預金も、きちんと金額を書いておけば安心よね?」
そう思って遺言書を作る方は少なくありません。
けれど実は、金額をそのまま書くことで、かえってご家族に負担やトラブルを残してしまうことがあるのです。
私がこれまでご相談を受けた中でも、預貯金の金額を書いた遺言が原因で、兄弟や親族が揉めてしまったケースは何度もありました。
ここでは、よくある3つのトラブルを、実際にあった事例と一緒にご紹介します。
1. 金額が増えてしまった場合
遺言書を書いたときより、預金が増えることは珍しくありません。
ところが、増えた分が遺言に書かれていないと、その部分は遺言の対象外になり、相続人全員で話し合う必要が出てきます。
この「遺産分割協議」は、全員の同意がないと決まらないため、仲の良いご家族でも気まずくなってしまうことがあります。
事例
Kさん(78歳・横浜市)は、3年前に「○○銀行の預金1,500万円を長男に渡す」と遺言に書きました。
相続の時点で残高は2,000万円に。増えた500万円の扱いが書かれていなかったため、兄妹で話し合いが必要になり、関係がぎくしゃくしてしまいました。
2. 金額が減ってしまった場合
逆に、病気や生活費などで預金が減ってしまうこともあります。
このとき「不足分を他の財産から補うのか、それとも減ったまま渡すのか」で解釈が分かれ、争いになることがあります。
事例
Mさん(74歳・川崎市)は、長女に「○○銀行の預金1,000万円を渡す」と書きましたが、亡くなる直前には残高が700万円に減少。
長女は「不足分をほかの財産から補ってほしい」と主張しましたが、兄弟たちは納得せず、話し合いが長引いてしまいました。
3. 遺言の思いが正しく伝わらない
金額を指定することで、あなたが本当に望んでいた分け方が実現できない場合もあります。
「お世話になったから多めに渡したい」そんなお気持ちが、金額の変動によって崩れてしまうこともあるのです。
私は、遺言は「家族を守るための贈り物」だと考えています。
せっかく残すなら、ご家族が安心できる形にしてほしい。
だからこそ、このようなトラブルにならないよう、書き方には工夫が必要です。
次の章では、なぜ預貯金額を遺言書に書かない方が良いのか、その理由と安全な方法を、やさしく解説します。
第2章:なぜ預貯金額を遺言書に書かない方が良いのか
預貯金額をはっきり書いたほうが、ご家族にとって分かりやすいのでは?
そう思うお気持ちはとてもよく分かります。
でも実は、金額をはっきり書くことで、かえって相続の場がややこしくなることがあります。
ここでは、その理由をわかりやすくお伝えします。
理由1:預金の金額は常に変わるから
預貯金は日々動きます。年金の入金、生活費や医療費の引き出し、定期預金の解約…
遺言書を書いたときの金額と、実際に相続が始まるときの金額は、ほとんどの場合違ってきます。
もし遺言に「○○銀行の預金1,000万円を長男に渡す」と書いていても、
亡くなる時に残高が950万円だったら?
あるいは1,200万円に増えていたら?
その差額の扱いが遺言に書かれていないと、家族同士で話し合う必要が出てきます。
理由2:解釈の違いで家族が揉める可能性があるから
お金の話は、たとえ仲の良い家族でも感情的になりやすいものです。
「不足分は他の財産から補ってあげたい」と思う人もいれば、
「書いてある金額だけ渡せばいい」と考える人もいます。
この違いが、争いのきっかけになってしまうことがあります。
理由3:せっかくの遺言が“無駄”になることも
預金の金額をはっきり書いた遺言でも、実際にはそのとおりに分けられず、結局は遺産分割協議(家族全員での話し合い)が必要になるケースもあります。
そうなると「遺言で全部決まっているから安心」という状態にはならないのです。
私はこれまで、「遺言を作ったから安心」とおっしゃっていた方が、実際の相続時に「結局、家族が揉めてしまった」と残念そうに話される場面を何度も見てきました。
そんな思いを避けるためにも、金額ではなく**“割合”で指定する方法**が安全です。
次の章では、その安全な書き方の具体例を事例と一緒にご紹介します。
第3章:安心して預貯金を遺すための安全な書き方
金額の変動によるトラブルを避けるためにおすすめなのが、金額ではなく“割合”で書く方法です。
割合で指定すれば、残高が増えても減っても、常にその割合で分けられるため、余計な話し合いを防ぐことができます。
1. 割合で指定する書き方の例
例えば、次のように書く方法があります。
《文例》
遺言者が死亡時に有する全ての預貯金の合計額の2分の1を長女〇〇〇〇に、同じく2分の1を長男△△△△に相続させる。
この書き方なら、残高が増えても減っても、そのときの金額を半分ずつに分けることができます。
2. 最低限の金額を保証する書き方
「割合で分けるだけだと、もし大きく減ってしまったら心配…」という方もいらっしゃいます。
そんな場合には、割合指定に“最低保証額”を組み合わせることもできます。
《文例》
遺言者が死亡時に有する全ての預貯金の合計額の3分の2を長女〇〇〇〇に、3分の1を長男△△△△に相続させる。
ただし、長女が相続する預貯金の額が300万円未満となる場合には、300万円を長女に相続させ、残りを長男に相続させる。
こうすれば、残高が減っても最低限の金額は守ることができます。
3. 実際のご相談事例
事例
Aさん(76歳・横浜市)は、長年一緒に暮らして介護をしてくれた姪に多めに遺したいと考えていました。
預貯金の額をそのまま書くと減ったときが不安…ということで、
「全預貯金の3分の2を姪に、残りを甥に。姪への取り分が300万円を下回る場合は必ず300万円を渡す」という形にしました。
この書き方であれば、どんな金額の変動があっても希望どおりに渡せることに安心されたそうです。
4. 安全な書き方のポイント
- 金額ではなく割合で指定する
- 必要に応じて最低保証額を入れる
- 銀行別・口座別に分ける場合も、金額ではなく口座単位や割合で指定する
- 迷ったら、必ず専門家に相談してから書く
私は「遺言は家族への最後のプレゼント」だと考えています。
だからこそ、作ったあとに家族が迷わない形に整えることが大切です。
次の章では、銀行別・口座別で分けたい場合の書き方をご紹介します。
第4章:銀行別・口座別で分けたい場合の書き方
「預金は銀行ごと、あるいは口座ごとに分けて指定したい」というご希望もよくあります。
例えば、長年取引のある銀行の預金は長男に、別の銀行の預金は長女に…といった形です。
この場合も、金額ではなく銀行や口座単位での指定が安全です。
1. 銀行別に指定する文例
銀行単位で指定する場合は、次のように書きます。
《文例》
第1条 遺言者は、死亡時に有するA銀行のすべての預金を長男〇〇〇〇に相続させる。
第2条 遺言者は、死亡時に有するB銀行のすべての預金を長女△△△△に相続させる。
この方法なら、残高の増減があっても銀行ごとに丸ごと渡せます。
2. 口座別に指定する文例
特定の口座を誰に渡すか決めておきたい場合は、支店名や口座番号まで書きます。
《文例》
第1条 遺言者は、死亡時に有する下記の口座を長女〇〇〇〇に相続させる。
A銀行B支店 普通預金 口座番号×××××××
第2条 遺言者は、死亡時に有する下記の口座を長男△△△△に相続させる。
C銀行D支店 普通預金 口座番号×××××××
こうしておけば、「どの口座を誰に渡すか」が明確になり、相続時の混乱を防げます。
3. 注意点
- 銀行名や支店名、口座番号は正確に書く
- 口座を解約した場合は、その遺言条項が無効になることがある
- 残高の変動は避けられないため、必要に応じて割合指定や最低保証額と組み合わせると安心
事例
Hさん(79歳・鎌倉市)は、長年応援してくれた妹に特定の口座を渡したいと考えていました。
金額は書かず、口座番号まで特定して遺言に記載。さらに「残高が300万円未満になった場合は他の口座から補う」と条件を付けました。
その結果、亡くなった後も希望どおりに妹へ遺すことができ、ご家族も安心されたそうです。
銀行別・口座別の指定は、正しく書けばとても有効です。
次の章では、遺言書を書く際に注意すべきその他のポイントと、トラブルを防ぐための最後のチェックリストをご紹介します。
第5章:遺言書を書くときに気を付けたいポイントと安心チェックリスト
遺言書は、一度書けば終わりではありません。
せっかく作ったのに、あとで「これでは使えない」となってしまっては意味がありません。
ここでは、トラブルを防ぎ、安心して残せる遺言書にするための大切なポイントをお伝えします。
1. 最新の情報に更新する
預貯金の口座や残高、不動産の状況は時間とともに変わります。
数年前に作った遺言が、今の状況に合っていないこともあります。
目安は2〜3年に一度の見直し。
「何も変わっていない」と思っても、確認しておくと安心です。
2. 法的に有効な形式で作る
せっかくの遺言も、法律の形式に沿っていないと無効になることがあります。
- 自筆証書遺言は全文手書き(財産目録を除く)、日付、署名、押印が必要
- 公正証書遺言なら、公証人が形式を整えてくれるので安心
3. 書き方に迷ったら専門家に相談する
「自分でできるから大丈夫」と思っていても、細かい部分で解釈が分かれる書き方になっていることがあります。
専門家に見てもらえば、“自分の希望どおりに確実に遺せるか”を確認できます。
4. 家族への気持ちも添える
遺言書は財産を分けるためだけでなく、感謝の気持ちや想いを伝える場でもあります。
「ありがとう」の一言が、ご家族の心を温かくします。
財産分けの条項と一緒に、付言事項として気持ちを書き添えるのもおすすめです。
遺言書・安心チェックリスト
- 預貯金は金額ではなく割合で指定している
- 銀行名や口座番号は正しく書いている
- 条項があいまいになっていない
- 作成から2〜3年以内に見直している
- 感謝や想いを付言事項で残している
- 必要に応じて専門家に確認している
私は、遺言書を作ることは今を安心して生きるための準備だと思っています。
まだご自身で判断できるうちに、ご家族のための準備を整えておくことができます。
まとめ|遺言書は「家族への思いやり」を形にするもの
遺言書に預貯金額をそのまま書くことは、一見わかりやすそうですが、実は金額の変動によってトラブルの原因になることがあります。
金額ではなく割合で指定する、必要に応じて最低保証額をつける、そして銀行別・口座別に正しく書くことで、安心して想いを遺すことができます。
今日お伝えした大切なポイント
- 預貯金額は金額でなく割合で指定する
- 必要に応じて最低保証額を設定する
- 銀行別・口座別の指定も有効
- 2〜3年に一度は見直す
- 感謝や想いを付言事項で残す
遺言書は、財産を分けるだけの書類ではありません。
あなたの想いと家族への思いやりを未来に届ける、大切な贈り物です。
「まだ元気だからこそ」冷静に考え、確実に実現できる形に整えておくことが、ご家族への安心につながります。
私は女性行政書士として、法律面だけでなくお気持ちにも寄り添いながら、遺言作成のお手伝いをしています。
「書き方がよく分からない」「自分の場合はどうすればいいの?」という方は、どうぞ一度お気軽にご相談ください。
あなたの想いを形にするお手伝いを、心を込めていたします。
横浜市で遺言書作成のご相談はお気軽に
横浜市を中心に、女性行政書士として法律面はもちろん、お気持ちにも寄り添いながらサポートいたします。
初回相談は60分無料(要予約)です。
電話・メールからお気軽にご連絡ください。
【お問い合わせフォーム】または【お電話:045-232-4491】
あなたの想いを、確実に未来へつなげるお手伝いをいたします。