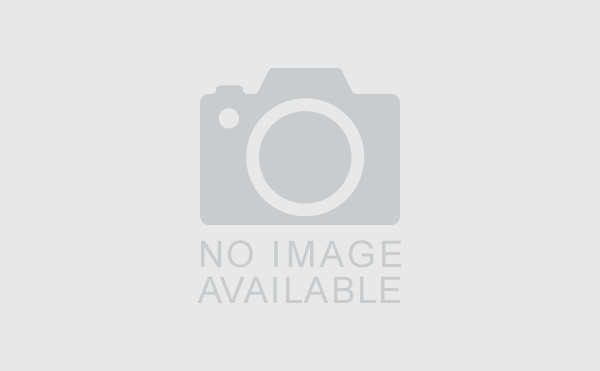遺言は何度でも書き直せる?公正証書から自筆に変えるときのポイント
「遺言書って一度作ったらもう直せないんでしょうか?」
「公正証書で作ったけれど、あとから自分で書き直しても大丈夫?」
横浜市にお住まいの70代女性から、こんなご相談をよくいただきます。
遺言は“最後の意思”ですから、一度作ったらやり直しがきかないのではと不安になるのも自然なことですよね。
でもご安心ください。遺言は何度でも書き直すことができます。
ただし、公正証書遺言から自筆証書遺言に変更する場合には、いくつか気を付けたいポイントがあります。
この記事では、女性行政書士の立場から、法律の知識だけでなく「ご不安なお気持ち」にも寄り添いながら、公正証書から自筆への書き直しについてわかりやすく解説します。
第1章:遺言は何度でも書き直せる
遺言書は、一度書いたらずっとそのままというわけではありません。
遺言は何通でも作成できますし、その中で一番新しい日付のものが有効となります。
たとえば、5年前に公正証書遺言を作ったとしても、その後に自筆証書遺言を書けば、日付が新しい自筆証書遺言が有効になります。
これは「古い遺言は、新しい遺言で取り消された」と考えるからです。
事例(横浜市70代女性)
「夫と一緒に公正証書遺言を作っていたけれど、今になって内容を少し変えたい。でも費用や手間を考えると、公正証書をもう一度作るのは大変で…」というご相談を受けたことがあります。
この場合でも、新しい自筆証書遺言を作れば、その遺言が有効になります。
つまり、「公正証書だから優先される」というわけではなく、**形式に優劣はなく“新しい日付が勝つ”**のです。
ただし、自筆証書遺言には「検認の手続きが必要」「形式の不備で無効になることがある」といった注意点があります。
次の章では、公正証書遺言から自筆証書遺言へ書き直すときに、特に気を付けたいポイントをお伝えします。
第2章:公正証書遺言から自筆証書遺言に変えるときの注意点
「費用や手間を考えると、公正証書ではなく、自分で書き直した方がいいかしら?」
そんなふうに思われる方もいらっしゃいます。
確かに、自筆証書遺言は自分で紙とペンさえあれば書けるので、身近で手軽に感じますよね。
でも、公正証書遺言から自筆に変更するときには、気を付けていただきたいことがいくつかあるのです。
1. 公正証書遺言の内容を確認する
まずは、以前に作成した公正証書遺言の内容をきちんと確認しましょう。
そのためには、公正証書遺言の「謄本(コピー)」が必要です。
もし紛失してしまった場合でも、公証役場に行けば再発行してもらえます。
ポイント
- 本人が公証役場に出向く必要がある
- 実印・印鑑証明書・身分証明書を持参
- 事前に公証役場へ電話確認をするとスムーズ
2. 自筆証書遺言は「形式不備」で無効になるリスクがある
自筆証書遺言には、法律上のルールが細かく定められています。
たとえば、全文を自書(手書き)すること、日付を書くこと、署名・押印をすることなど。
一つでも要件を欠くと、せっかく書いても無効になってしまうのです。
「これで大丈夫」と思っていても、実際には細かい部分で間違えてしまう方は少なくありません。
3. 検認の手続きが必要
自筆証書遺言は、亡くなったあとに家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
これがご家族にとって手間になることがあります。
公正証書遺言なら検認は不要ですが、自筆に変えた場合にはご家族が裁判所に出向く必要があることも知っておきましょう。
4. 専門家のチェックを受けると安心
「それならやっぱり自分では難しいかも…」と思われた方もいるかもしれません。
でもご安心ください。自筆証書遺言であっても、作成の段階で専門家に確認してもらえば、無効になるリスクを大きく減らすことができます。
私は女性行政書士として、形式的な部分のチェックはもちろん、「ご家族に本当に伝わる内容になっているか」まで一緒に見直します。
文字の大きさや言葉の選び方ひとつで、読み手の受け取り方は変わります。
だからこそ、法律の専門家と一緒に仕上げることが大切です。
5. 法務局の「遺言書保管制度」を活用する方法もある
「自筆証書遺言は無効になるリスクがあるし、家族に見つけてもらえるか不安…」
そんな方におすすめなのが、法務局の遺言書保管制度です。
これは、自分で作った自筆証書遺言を、法務局で預かってもらえる制度です。
預けることで、次のような安心が得られます。
- ご家族が遺言を探す手間がなくなる
- 裁判所での検認が不要になる
- 紛失や改ざんの心配がない
横浜市内にも遺言書保管所となる法務局があり、そこで手続きが可能です。
費用も数千円程度と、公正証書遺言より負担は少なく済みます。
ワンポイント
「費用や手間を減らしたい」けれど「無効や紛失は不安」という方は、
法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言という選択肢もあります。
私は、70代の女性から「子どもに迷惑をかけたくないから、法務局に預けておこうと思う」という声をよくいただきます。
遺言の内容と一緒に「保管制度を使うかどうか」も検討してみると安心です。
第3章:70代女性がよく迷う「公正証書か?自筆証書か?」の場面別比較
遺言のご相談を受けるとき、特に70代の女性が悩まれるのは「公正証書にすべきか、自筆にすべきか」という選択です。
どちらも効力に優劣はありませんが、状況によって向いている方法が変わります。
ここでは実際のご相談のやりとりを交えて比べてみましょう。
1. 「子どもに迷惑をかけたくない」
ご相談者(横浜市在住・70代女性):
「子どもに余計な手間をかけたくないんです。亡くなったあとにスムーズに進むようにしておきたいのですが…」
行政書士(私):
「そのお気持ち、とても大切ですね。公正証書遺言なら検認が不要で、すぐに相続の手続きに使えます。
もし費用や手間を抑えたい場合は、自筆で書いたうえで法務局に預ける制度を使えば、同じように検認が不要になり安心ですよ。」
おすすめ:ご家族に負担をかけたくない方は、公正証書遺言か、自筆+法務局保管制度が安心です。
2. 「費用を抑えて、気軽に書き直したい」
ご相談者:
「財産はそんなに多くないので、できれば費用はあまりかけたくないんです。でも内容は時々変えたいと思っていて…」
行政書士:
「それなら自筆証書遺言が向いていますね。紙とペンがあればいつでも書き直せますし、法務局に預ければ安心感も増します。
公正証書は確実ですが、その分、作成や変更には数万円の費用がかかります。」
おすすめ:費用を抑えて柔軟に書き直したい方は、自筆証書+法務局保管制度が合っています。
3. 「不動産や複数の預金がある」
ご相談者:
「不動産もあるし、預金も複数の銀行にあります。自分で書いたら間違えそうで…」
行政書士:
「その場合は公正証書遺言の方が安全です。登記事項証明書や口座情報を確認して作成するので、不備が出にくいんです。
自筆で書くと、表現の曖昧さや記載漏れで無効になる可能性があります。」
おすすめ:財産が複雑な方は、公正証書遺言が安心です。
4. 「今は元気だけど、将来が心配」
ご相談者:
「今は元気だけど、将来、判断力が落ちてきたらどうしようと不安です…」
行政書士:
「ご心配はもっともです。自筆証書遺言だと、後から“本当に本人が書いたのか”と争われることもあります。
公正証書遺言なら、公証人が立ち会って作成するため有効性を疑われにくいですよ。
また、最近は法務局の保管制度を使って自筆証書遺言を預ける方法もあります。これなら紛失や改ざんの心配がなく、検認も不要です。
ただし、相続が始まった後にご家族が遺言書を使う際には、**戸籍謄本などの書類を集めて「遺言書情報証明書の交付請求」や「閲覧請求」**をしなければならず、一定の手間がかかるという点も覚えておきましょう。」
おすすめ:将来を見据えて確実に残したい方は、公正証書遺言が一番安心。
費用や柔軟性を重視するなら、自筆証書+法務局保管制度を検討してもよいですが、「ご家族の手間」が少し残ることは理解しておく必要があります。
女性行政書士からひとこと
どの方法を選ぶかは「費用」「ご家族への負担」「財産の内容」「ご自身の体力やお気持ち」で変わります。
私は女性ならではの目線で、法律的な正確さと、残す方の想いの両方を大切にしながら、一緒に最適な方法を考えていきます。
まとめ|大切なのは「形式」よりも「想いを確実に伝えること」
遺言には、公正証書でも自筆証書でも「どちらが優れている」という優劣はありません。
大切なのは、ご自身の想いをきちんとご家族に伝えられるかどうかです。
- 公正証書遺言なら、確実で安心。検認も不要でご家族の負担が軽い。
- 自筆証書遺言なら、費用がかからず気軽に書き直せる。
- 法務局の保管制度を使えば、自筆証書でも検認が不要になり、紛失や改ざんの不安も減らせる。
どの方法が良いかは、「費用」「財産の内容」「ご家族への思いやり」によって変わります。
私は女性行政書士として、形式的なアドバイスだけでなく、“残す方の気持ち”にも寄り添いながら最適な方法をご提案しています。
横浜市で遺言書作成のご相談はお気軽に
横浜市を中心に活動しており、初回相談は60分無料で承っております。
法律面のご説明はもちろん、「子どもに迷惑をかけたくない」「自分に合った方法がわからない」といったお気持ちにも丁寧にお応えします。
【お問い合わせフォーム】または【お電話:045-232-4491】
どうぞお気軽にご相談ください。
あなたの想いを、確実に未来へ届けるお手伝いをいたします。