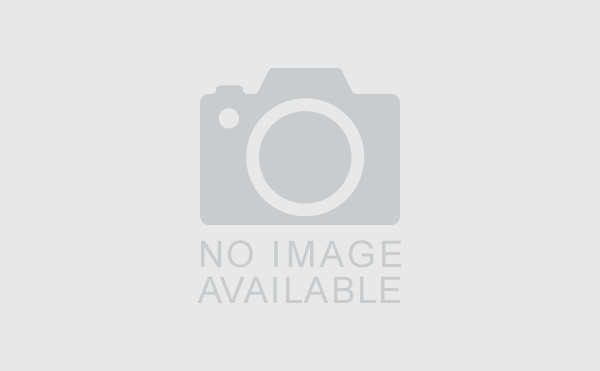70代おひとり様の“もしも”の備え|任意後見とは
第1章 「元気なうちに、準備しておけばよかった…」と思わないために
年を重ねると、誰しも「この先、もしものことがあったらどうしよう」と不安になるものです。
特に、子どもがいないおひとり様・おふたり様にとっては、いざというときに頼れる人が限られているからこそ、将来の備えがより重要になります。
「まだ元気だから大丈夫」「困ったときに誰かが何とかしてくれるはず」
そう思って先延ばしにしてしまう方は少なくありません。
けれど、判断力が衰えたり、病気で入院したりしたとき、代わりに手続きしてくれる人がいないと…
・銀行口座が凍結されてお金が引き出せない
→ 入院費や生活費が払えなくなることがあります。
・施設に入る契約ができない
→ 本人が契約できないと、入所できないケースも。
・悪質な訪問販売で高額契約をしてしまった
→ 誰かが止めてくれる環境がないと、被害が拡大してしまうこともあります。
——こうしたリスクが、実際に多くの高齢者に起きています。
「まだ起きていない将来のこと」は、つい後回しにしがちです。
でも、いざというときには、もう自分で判断したり、決めたりすることができなくなってしまうかもしれません。
そうなってからでは、残念ながら遅いのです。
だからこそ、「元気なうちに備えておける仕組み」が大切です。
それが、今のあなたにできる【任意後見制度】という備えなのです。
第2章 任意後見制度とは?|70代から考える「自分で選べる安心」の備え
任意後見制度とは、将来あなたの判断力が低下したときに備えて、あらかじめ信頼できる人に「代理の権限」を託しておく制度です。
認知症や病気などで自分の意思がはっきりしなくなったとき、通帳の管理や施設の契約、役所での手続きなど——日常生活に欠かせない事務を、代わりに行ってもらうことができます。
この制度の大きな特徴は、**「自分で選んだ人に、将来の判断を委ねることができる」**という点。
たとえば、こんな希望にも対応できます:
- 近所に住む甥に手続きをお願いしたい
- 親身に話を聞いてくれる知人に頼みたい
- 子どもがいないので専門職(行政書士など)に任せたい
→ 任意後見では、自分が「信頼できる」と思う人を、自由に選ぶことができます。
任意後見は、公正証書で契約を交わし、その後、ご本人の判断力が低下した段階で家庭裁判所が「後見監督人」を選任することで正式にスタートします。
つまり、「契約は元気なうちにできる」「実際に動き出すのは必要になったとき」——それが任意後見制度の大きな特徴です。
▼ 任意後見と法定後見の違い|選べる安心と選べない不安
任意後見と混同されがちな制度に、「法定後見」があります。
こちらは、すでに本人の判断能力が不十分になってから、家族などが家庭裁判所に申し立てることでスタートします。
選ばれる後見人は、必ずしも希望した人になるとは限らず、弁護士や第三者が選ばれることもあります。
| 比較項目 | 任意後見 | 法定後見 |
| 開始時期 | 判断力があるうちに契約 → 将来発効 | 判断力が衰えたあとに申し立て |
| 後見人の選び方 | 自分で選べる | 裁判所が選ぶ |
| 契約方法 | 公正証書で契約 | 家庭裁判所の審判 |
「自分で、今のうちに備えたい」
「自分の想いを尊重してくれる人に任せたい」
そう思う方にとって、任意後見はまさに“自分らしい選択”ができる制度です。
第3章 法定後見制度との違い|なぜ任意後見のほうが安心なのか?
「困ったときには、誰かが後見制度を使って助けてくれるのでは?」
そう考えている方も少なくありません。
たしかに、認知症や病気などで判断能力が低下したときには、家庭裁判所に申し立てることで「法定後見制度」を利用することができます。
けれど――実は、法定後見制度には“自分の希望が通らない”という大きなデメリットがあるのです。
たとえば…
- 誰が後見人になるか、自分では決められません。
→ 弁護士や司法書士などまったく面識のない第三者が選ばれることもあります。 - 日常のサポート内容や財産の使い道、ライフプランなどを、自分で細かく決めておくことができません。
→家庭裁判所の判断によって制限される場合があり、自由度が下がります。
つまり、「いざというときに助けてくれる人がいる」安心感はあっても、必ずしも“自分が望む形”になるとは限らないのです。
任意後見制度であれば、自分が元気なうちに、信頼できる人に「どこまで・何を」任せるかを自由に決めておけます。
しかも、
・どんなことをお願いしたいか(財産管理・医療・施設手続きなど)
・どこまで任せたいか
など、契約内容をあらかじめ自分で細かく決めておけるのが大きな特徴です。
「こんなときには、こうしてほしい」——
その想いを、文書にしてきちんと残しておくことで、
あなたの“意思ある老後”を、最後まで守ることができるのです。
第4章 任意後見は「今」がチャンス|準備すべき3つのタイミングとは?
任意後見制度は、「自分でしっかり判断できる今」のうちにしか契約できません。
だからこそ、「そのうち」ではなく、「今このタイミング」がとても大切なのです。
では、どんなときに準備を考え始めるべきなのでしょうか?
ここでは、任意後見を検討すべき【3つのタイミング】をご紹介します。
① 70代に入ったとき
年齢とともに、判断力の変化は誰にでも起こり得ます。
実際、任意後見契約をされる方の多くは70代。
「まだ元気なうちに備えておきたい」という方が、早めの準備を始めています。
② 健康に不安を感じ始めたとき
高血圧・糖尿病・軽度の認知症など、「ちょっと心配…」と思う変化が出てきたら、準備のタイミングです。
とくに認知症の場合、判断能力の低下が進むと任意後見契約ができなくなってしまうため、「まだ大丈夫」と思っているうちに行動することが大切です。
③ 頼れる家族がいないと気づいたとき
おひとり様や、おふたり様で子どもがいない方の場合、
「いざというときに誰が手続きしてくれるのか」が大きな不安要素になります。
たとえば…
・介護施設の入所契約
・財産管理や支払い手続き
・病院の入院・退院手続
・要介護認定の申請支援
こうした場面で、「誰にも頼めない…」となってしまわないように、信頼できる人と事前に契約を結んでおくことが、将来の安心につながります。
「今はまだ大丈夫」——でも、“その時”は、ある日突然やってくるかもしれません。
元気な今こそが、一番行動しやすいタイミングです。
あなた自身の意思で、安心できる備えを始めてみませんか?
第5章 任意後見を準備していなかった人の末路|よくある5つのトラブル事例
「こんなことになるなんて…もっと早く準備しておけばよかった」
任意後見のご相談を受ける中で、私たちはこのような声を何度も耳にしてきました。
任意後見制度は、判断能力があるうちしか契約できないため、元気なうちに備えておくことが大切です。
けれど、いざという時にはじめて制度の必要性に気づき、手遅れになってしまう方も少なくありません。
ここでは、実際にあった「困ったケース」を5つご紹介します。
① 認知症が進行してからでは遅かった
ご相談に来られたのは、70代女性の姪御さん。
「最近、叔母の様子が変なんです」と来所されましたが、すでに認知症が進んでおり、医師の診断で“契約能力なし”と判断されました。
結局、希望どおりの任意後見は使えず、「法定後見」の申し立てに。
時間も費用もかかり、本人の希望も通しにくくなってしまいました。
② 訪問販売で高額な買い物をしてしまった
一人暮らしの80代女性が、複数の健康器具を次々と契約。
業者に勧められるまま契約書にサインしてしまい、総額は数百万円に。
家族が気づいたときには解約も難しく、金銭的被害が深刻に。
任意後見人がいれば、契約前に気づき、防げた可能性があります。
③ 施設に入れなかった
要介護状態になり、入所を希望したものの、本人が署名できず、代わりに手続きできる家族もいない。
施設側も「後見人が必要です」と対応を断るしかなく、結果として入所が大幅に遅れてしまいました。
④ 入院費が払えなかった
急な入院で本人が手続きできず、兄弟が銀行口座を動かせない状況に。
病院に支払いを待ってもらいながら、後から法定後見を申し立てることに。
親族にも精神的・経済的な負担が大きくのしかかりました。
⑤ 家族でもめて、希望と違う人が後見人に
本人が判断できない状態になったあと、兄弟で「誰が後見人になるか」で揉めました。
話がまとまらず、家庭裁判所が第三者の専門職(司法書士)を選任。
兄弟も本人も納得できず、不満を残す結果に。
こうした問題は、「元気なうちに」「信頼できる人と」備えておけば、防げることがほとんどです。
「まだ大丈夫」——そう思っている今だからこそ、実は一番スムーズに備えができるタイミングです。
将来のあなたを守るのは、今のあなたの“ひとつの行動”かもしれません。
6章 子どもがいない人こそ備えておきたい|任意後見が必要な5つの理由
「子どもがいないから、老後のことが心配で…」
「夫婦ふたりとも高齢だから、どちらかが倒れたときが不安です」
そんな声が、近年ますます増えています。
実は、任意後見制度は「おひとり様」や「子どものいないご夫婦」こそ、特に活用してほしい制度です。
【1】頼れる身内がいない——そんなとき、誰が代わりに動いてくれる?
入院や施設入所、年金や預金の手続きなど。
「いざ」というとき、本人の代わりに動いてくれる人がいなければ、手続きが止まってしまいます。
「誰かが助けてくれるだろう」では済まないのが、現実です。
【2】知らない第三者が後見人になる可能性も…
法定後見では、家庭裁判所が後見人を決めます。
家族がいても「不適任」と判断されれば、弁護士などの第三者が選ばれるケースも。
一方、任意後見なら自分で信頼できる人を指名しておけるため、「希望通り」に進められる安心があります。
【3】元気な今しか、任意後見は契約できません
任意後見は、「本人に判断能力があるうち」でないと契約できません。
だからこそ、「まだ大丈夫」と思える今のうちに、備えておくことが重要なのです。
【4】“将来”だけじゃない。「今」からサポートが受けられる
任意後見とあわせて「見守り契約」「財産管理委任契約」を結ぶことで、判断力があるうちからサポートを受けることができます。
たとえば:
・通院や手続きの付き添い
・公共料金や家賃の支払い代行
・不審な契約のチェックや助言
「まだ元気だけど、少し心細い…」という方にも安心の体制が整えられます。
こうした「まだ元気だけど、ちょっと不安」にも対応できるのが、任意後見とその周辺契約の強みです。
【5】「自分らしい老後」のために、今できる選択を
誰に手伝ってほしいか、どんな生活を送りたいか——
それを、自分で決めておけるのが任意後見の最大のメリットです。
子どもがいなくても、頼れる人がいなくても、
「ちゃんと準備してきたから大丈夫」と思える安心を、ぜひ手に入れてください。
第7章 任意後見の備えは「今この瞬間」から始められます
人は誰しも年齢を重ねれば、誰かの助けが必要になる日が訪れます。
でも、判断力が落ちてからでは任意後見契約はもう結べません。
法定後見になると、希望していない第三者が選ばれたり、財産の使い方に制限がかかったりすることもあります。
いざというときに頼れる人がいなければ、せっかくの老後が“思い通りにいかない”ものになってしまうかもしれません。
そんなリスクを、「まだ大丈夫」と見過ごしてしまうのは、あまりにももったいないことです。
任意後見は、“今のあなた”だけが使える制度
まだ元気なうちだからこそ、
自分で、信頼できる人を選び、
自分らしい未来を準備することができます。
「子どもがいないからこそ」
「夫婦ふたりだけだからこそ」
必要な備えがあります。
安心して老後を迎えるために
任意後見は、あなたが将来困らないための「お守り」のようなもの。
- 自分で選んだ人に託すことができる
- 必要なときにサポートがスタートする
- 財産や生活を“知らない誰か”に任せずに済む
そんな「安心して老後を迎えるための選択肢」を、今こそ考えてみませんか?
まずは一歩を踏み出すことから
「まだ急がなくても大丈夫」と思っている今こそが、実は備えにぴったりのタイミングです。
何から始めればよいか分からない方も、ご安心ください。
ご相談いただければ、あなたの状況に合わせて、一緒に“将来の安心”をつくっていくお手伝いをいたします。
“そのとき”が来る前に、あなたらしい安心を手に入れましょう。
無料相談・ご予約はこちらから
【お問い合わせフォーム】または【お電話:045-232-4491】
横浜で相続や遺言のご相談なら、経験豊富な行政書士が丁寧に対応いたします。
未来の安心のために。
まずは一歩、踏み出してみませんか?