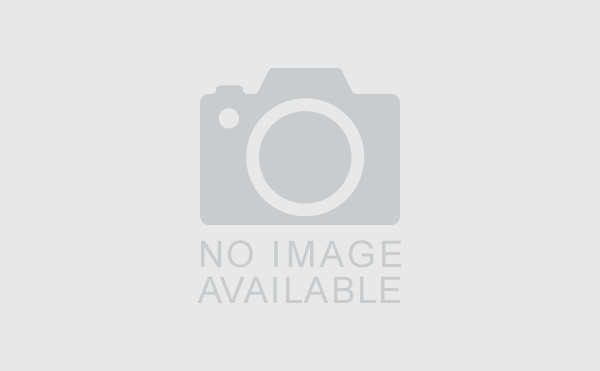おひとりさまの相続対策|身寄りがない人のための遺言と死後の備え
はじめに:こんな不安はありませんか?
「自分が亡くなったあと、誰が手続きをしてくれるのだろう」
「身寄りがないから、葬儀や家の片づけが心配」
「遺言書を残した方がいいとは聞くけれど、何から始めればいいかわからない」
――そんな不安を抱えている「おひとりさま」は、決して少なくありません。
実際、家族や親戚と疎遠になっていた方が亡くなり、関わっていた知人が葬儀を手配しようとしても、法的な手続きができずに困ってしまったという相談を受けたことがあります。
相続人が不明なまま放置されてしまい、片付けや手続きが進まないケースもあるのです。
けれど、きちんと準備をしておけば、そんな不安は大きく減らすことができます。
この記事では、**「遺言書」と「死後事務委任契約」**という、2つの備えについて解説していきます。
「こんな方法があるんだ」「私も準備しておこう」――
そう思ってもらえるように、わかりやすくお伝えしますね。
1. 遺言書を作るべき理由とは?
おひとりさまの相続対策において、まず考えていただきたいのが「遺言書」の作成です。
理由①:相続人が兄弟や甥・姪になるケースが多い
ご自身に子どもや配偶者がいない場合、相続人は「直系尊属(親)」になります。親がすでに他界している場合には、次に兄弟姉妹が相続人となります。
実際には、両親もすでに亡くなっているケースが多く、その場合の相続人は「兄弟姉妹」、そして兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子ども(甥・姪)になります。
しかし、すでに長く連絡を取っていなかったり、どこにいるか分からなかったりする方も多いのではないでしょうか。
相続人が見つからなければ、遺産の手続きが進まずに長期間放置されることもあります。
また、望まない相手に財産が渡ってしまう可能性もあるのです。
理由②:望む人に財産を残すことができる
「長年お世話になった友人に渡したい」
「信頼している団体に寄付したい」
そんな想いを実現できるのが、遺言書の力です。
法定相続人以外の人に財産を残すには、遺言書が必要です。
もし遺言がなければ、その願いは叶わないまま終わってしまうかもしれません。
理由③:自分の意思をきちんと伝えられる
遺言書には、財産の分け方だけでなく、気持ちや感謝の言葉を残すこともできます。
自分がどう生き、どんな想いを持っていたのか。
大切にしていたことや、託したい未来――それらをきちんと形にしておけるのが遺言書です。
このように、遺言書は「相続トラブルを防ぐため」だけではなく、
**「自分の人生の最後に、自分らしい決断を残す手段」**でもあるのです。
2. 死後事務委任契約とは?
「死後のことなんて、自分が亡くなった後のことだから考えたくない…」
そう思っている方もいるかもしれません。
けれど、家族がいないおひとりさまにとって、死後の準備はとても重要です。
その鍵となるのが、「死後事務委任契約」という制度です。
死後事務委任契約とは、自分が亡くなったあとに必要となる事務手続きを、信頼できる人にあらかじめ依頼しておく契約です。
たとえば、こんな手続きが対象になります:
病院や施設の退去手続き
電気・ガス・水道の解約
賃貸住宅の明け渡しや家の片付け
葬儀や納骨に関する手配
役所への届出関係 など
これらの手続きは、亡くなったあとに必ず発生するものです。
しかし、親族がいなければ誰もやってくれない可能性があります。
その結果、家が荒れたまま放置される、病院や施設に迷惑をかける――そんなケースも少なくありません。
実際にあったご相談から
ある相談者の方は、兄弟もおらず、長年の友人が心配して手続きを手伝おうとしてくれました。
けれど、相続人ではないため一切の手続きができず、大きな壁にぶつかったそうです。
せめて死後事務委任契約や遺言書があれば…と、友人の方が悔しそうに語っていました。
反対に、事前にきちんと準備をしていた別の方は、葬儀から財産の整理、希望する団体への寄付まで、すべてがスムーズに進みました。
亡くなったあとまで、自分の意思が形になるという安心は、大きな力になるのです。
死後の手続きを「誰かがやってくれるだろう」と思っていても、実際には「誰もできない」ことがある――。
だからこそ、死後事務委任契約と遺言書で、自分の希望を形にしておくことが大切です。
3. どんな準備をすれば安心なのか?
おひとりさまが安心して人生の最期を迎えるためには、
「死後の備え」と「財産の行き先」をあらかじめ決めておくことがとても大切です。
準備すべき主なものは、次の2つです。
① 死後事務委任契約
これは前の章で詳しくお伝えしたとおり、
亡くなったあとの手続きを信頼できる人に託しておく契約です。
・誰にお願いするのか
・何をやってもらうのか(葬儀・片付け・契約解除など)
・費用はどこから出すのか
これらを文書にして公正証書にしておけば、
実際に必要になったとき、迷いなく行動してもらえます。
「家族がいない自分のことを、誰が見てくれるのか」という不安が、
この契約によってひとつ、解消されます。
② 遺言書の作成
財産の行き先を決めるには、遺言書が必要です。
もし遺言がなければ、民法に従って、兄弟姉妹やその子ども(甥・姪)に相続されることになります。
ですが、交流のない親族に自分の財産を渡したいと思うでしょうか?
長年、支えてくれた友人に渡したい
お世話になった団体に寄付したい
死後の整理をしてくれる人に、きちんと残したい
こういった希望を実現するには、法的に有効な遺言書を作るしかありません。
「気持ちだけ伝えていた」では、相続の場面では効力がないのです。
4.今から準備することで、こんな安心が得られます
死後の手続きが滞らず、他人に迷惑をかけずにすむ
財産を大切な人や団体に、きちんと届けられる
「最後まで自分らしく」生きる選択肢をもてる
だからこそ――
「いつか」「そのうち」と思わず、
元気なうちにこそ、準備をしておくことが大切です。
5. よくあるご質問と不安の声
おひとりさまの相続や終活のご相談では、
「本当にこれでいいの?」という不安や疑問が多く寄せられます。
ここでは実際によくある声をご紹介しながら、一つひとつお答えしていきます。
Q1. 「まだ元気なのに、今から準備するのは早すぎませんか?」
A. むしろ「元気な今」がベストなタイミングです。
死後事務や遺言は、意思がはっきりしている今だからこそ、ご自身の希望を形にできます。
病気になってからでは判断能力が不安定になり、契約や遺言が無効になるリスクも。
備えは「万が一の前」が基本です。
Q2. 「頼れる人がいないのですが、誰にお願いすればいいですか?」
A. 血縁に限らず、信頼できる知人や専門職(行政書士・司法書士など)も選択肢になります。
死後事務委任は報酬を設定できるので、
「迷惑にならないだろうか…」と心配せずに依頼することが可能です。
Q3. 「遺言は自分でも書けると聞きましたが、専門家に頼んだほうがいいですか?」
A. 自筆の遺言でも有効ですが、形式の不備や記載ミスがあると無効になることがあります。
確実に実行してもらいたい場合は、公正証書遺言がおすすめです。
行政書士などの専門家がサポートすることで、安心して遺せます。
Q4. 「費用が高くなるのではと不安です…」
A. 死後事務委任契約や遺言書作成には費用がかかりますが、
その内容や依頼先によって大きく異なります。
一人ひとりの状況に合った内容で無理なく備えられるよう、事前の相談がおすすめです。
あなたと同じような不安を感じていた方も、
実際に準備をしておくことで「気持ちが軽くなった」「安心して過ごせるようになった」とおっしゃいます。
6. まとめ|おひとりさまこそ、人生の幕引きを自分で決める
家族がいない、自分の死後に迷惑をかけたくない――
そう思っていても、何もしなければ「誰か」が手続きをし、財産は法律に従って分けられてしまいます。
でも、
・遺言を作っておくことで、自分の意思で財産の行き先を決めることができます。
・死後事務委任契約を結んでおけば、葬儀や住まいの片付けなどを信頼できる人に託すことができます。
実際、ある70代の女性の方は、身寄りがないことをとても不安に感じておられました。 「もし自分が倒れたら、葬儀はどうなるのか」「部屋の片付けは誰がやってくれるのか」と悩み、当事務所にご相談にいらっしゃいました。 ご本人と何度も話し合いを重ね、信頼できる知人を代理人にした死後事務委任契約と、想いを込めた遺言書を作成。 「これでもう安心。今は趣味の旅行にまた行ける気持ちになったわ」と、晴れやかな笑顔を見せてくださいました。 このように、事前に準備を整えることで、日々の暮らしに安心と自由が戻ってくる方も多いのです。
だからこそ、
今のうちに、自分らしい最期の迎え方を考えておくことが、
“おひとりさま”にとっては何よりの安心につながります。
不安を抱えたままではなく、「これで大丈夫」と思える備えを、一歩ずつ一緒に整えていきましょう。
この記事が、少しでも「読んでよかった」と思っていただけたら嬉しいです。
もし具体的な相談をご希望の方は、お気軽にご連絡くださいね。
無料相談・ご予約はこちらから
【お問い合わせフォーム】または【お電話:045-232-4491】
横浜で相続や遺言のご相談なら、経験豊富な行政書士が丁寧に対応いたします。
未来の安心のために。
まずは一歩、踏み出してみませんか?