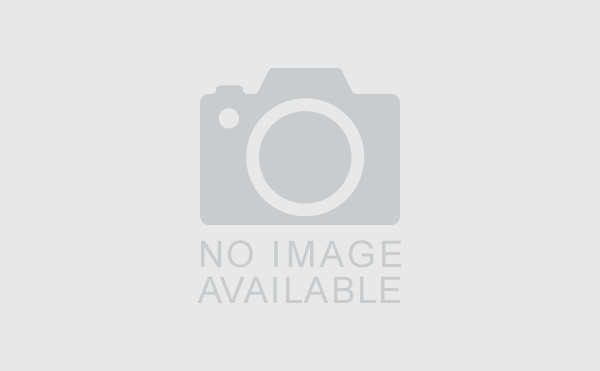子どもがいない人は遺言書が必須?知らないと兄弟に相続される3つの理由
遺言がないと兄弟に相続されるって本当?
はい、本当です。
民法では、相続人が「配偶者と子ども」だけでなく、子どもがいない場合は兄弟姉妹にも相続権があると定められています。
▽具体的にはこんなケースです
- 配偶者も子どもも親(尊属)もいない → 兄弟姉妹が法定相続人
- 兄弟姉妹も亡くなっている → その子ども(甥や姪)が相続する(代襲相続)
一見すると、兄弟に相続されるのは自然なことのように思えるかもしれません。
しかし、実際には「何十年も会っていない兄弟」「ほとんど知らない甥や姪」との遺産分割協議が必要になり、手続きが止まってしまうことも少なくありません。
🧾 実際にあった事例
「当然、夫婦で築いた財産は、自分が引き継げるものだと思っていました」
と語ってくださったのは、70代女性のAさん。
配偶者に先立たれたあと、相続手続きをしようとしたところ、法定相続人として出てきたのは、配偶者側の兄弟姉妹、さらに養子に出ていた兄弟まで含めた複雑な親族関係でした。
関係者の戸籍を取り寄せるだけでも手間と費用がかかり、
「何をどう調べればいいのかもわからず、ただただ混乱するばかり――。それが当時の私の正直な気持ちでした。」と振り返られています。
後になって、遺言があれば自分に全て相続させることも可能だったと知り、
「素人だからこそ、夫婦なら当然に引き継げると思ってしまった。知らなかったことが悔やまれる」とおっしゃっていました。
子どもがいない人が遺言書を作らないと困る3つの理由
遺言書がないと「誰がどれだけ相続するか」は法律に従って決まります。
けれど、それが必ずしも自分の想いや希望通りになるとは限りません。
特に子どもがいない方は、配偶者の兄弟や甥・姪など、普段交流のない人が相続人になることも多く、トラブルの火種になりやすいのです。
ここでは、実際によくある「遺言がないことで起きやすい3つの問題点」をご紹介します。
理由①:思い通りに財産を残せない
法律では、たとえ何十年も連れ添ったパートナーや、大切にしていた支援者がいても、
「法定相続人」以外には財産が渡らない仕組みになっています。
「兄弟や甥・姪に渡るくらいなら、お世話になった人に遺したかった」
そう思っても、遺言書がなければ、その希望は実現しません。
🧾 実際にあった事例:配偶者の連れ子に残したかったのに…
Aさんは、配偶者の連れ子であるBさん家族と長年生活をともにし、買い物や病院の付き添いなど、日々の世話はすべてBさんが担っていました。
生前、Aさんは何度も「私が死んだら、この家も財産も全部あなたにあげるからね」と口頭で伝えていたそうですが、遺言書を作る前に突然亡くなってしまいました。
結果として、法定相続人であるAさんの兄弟が全財産を相続することになり、どれだけ尽くしてきたとしても、Bさんには一切の権利がない――という現実だけが残りました。
「法律上は“他人”かもしれないけれど、何年も一緒に暮らして、支え合ってきた“家族”だったのに…」
と、Bさんは声を震わせながら、悔しさをこらえて語ってくださいました。
理由②:遺産分割協議(相続人全員の話し合い)が難航しやすい
遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議」という話し合いを行わなければなりません。
ところが、兄弟や甥姪が相続人に含まれると、連絡先が分からない、会ったこともない、というケースも多く、スムーズにいかないことがほとんどです。
このように、気持ちが通じていても、法的な裏付けがなければ実現しないのが現実です。
だからこそ、子どもがいない方や、法定相続人以外に財産を遺したい場合は、遺言書を残すことが必須なのです
また、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。
たった一人でも署名や押印を拒否したり、判断能力に問題がある場合、手続きはすべてストップしてしまいます。
🧾 実際にあった事例:認知症の兄弟が協議できず、5年かかったケース
ある方の相続では、兄弟および甥姪を含めた5人が相続人でした。
そのうちの1人である配偶者の兄弟が重度の認知症で、意思表示ができず、遺産分割協議ができない状態に。
本来であれば、その兄弟に「成年後見人」をつけて協議を進めるべきでしたが、
後見人の申立てには費用と時間がかかるため、現実的に難しく、協議は先延ばしに。
結局、その認知症の兄弟が亡くなり、代わって甥姪が相続人となった5年後にようやく協議が成立しました。
「家族の遺産なのに、何ひとつ進まず、もどかしさだけが募っていきました。最終的には心身ともに疲れきってしまいました。
最初から遺言書があれば、こんなに時間もお金もかからなかったのに…」
と、遺された家族は悔しさを滲ませていました。
このように、たった一人の署名がもらえないだけで、遺産が動かせなくなるのが現実です。
特に、高齢者同士が相続人になるケースでは、認知症や判断能力の問題が起こりやすくなっています。
理由③:遺言がないことで残された人が苦しむ
遺言書は、「自分のため」でもあり、同時に「残された人のため」でもあります。
とくに高齢になると、配偶者が先に亡くなった後、ひとりで相続手続きをするのは大変な負担です。
また、手続きの途中で亡くなってしまい、**相続が二重、三重になる“数次相続”**が起こると、相続人の数が増えてしまい、さらに複雑になります。
🧾 実際にあった事例:精神的に落ち込み、家も売れなくなったケース
ある方は、長年連れ添った配偶者を亡くし、精神的なショックでしばらく相続手続きができない状態が続いていました。
その間に、配偶者の相続人である兄弟の一部が認知症になったり、亡くなったりしてしまい、遺産分割協議が進まないまま年月だけが経過。
そのうちに自分の体調も悪くなり、「家を売って老人ホームに入りたい」と思った頃には、
遺産分割が終わっておらず、不動産の売却もできない状態になってしまっていたのです。
さらに、兄弟の死去により新たに相続人となった甥や姪たちからは、
「印鑑を押すなら“はんこ代”が必要だ」と言われ、余分な出費と時間がかかってしまいました。
「もし夫の兄弟が元気でいてくれたら、話し合いももっと早く進んだかもしれません。
けれど、現実は次々と状況が変わり、気づけば自分の体調まで悪くなってしまっていて…」
と、その方は肩を落としながら語ってくださいました。
このように、時間が経てば経つほど、相続の手続きは複雑に、精神的にも肉体的にも負担が大きくなっていくのが現実です。
だからこそ、遺言書で「誰に」「どの財産を」と明確にしておくことが、残される人を守る手段になるのです。
まとめ|「子どもがいない夫婦」だからこそ、遺言書は備えになる
子どもがいない夫婦にとって、遺言書は自分たちの意思を確実に反映できる、大切な手段です。
配偶者が亡くなった後、法定相続人が兄弟や甥姪になると、
・話し合いに時間がかかる
・認知症や死亡により相続人が変わっていく
・知らない相続人との手続きが必要になる
など、複雑で想定外のトラブルが起きがちです。
「家族がいないから簡単に済むだろう」
「兄弟がいないから心配ないと思っていた」
そう考えていた方ほど、あとから後悔されることが多いのです。
遺言書を作成しておけば、
・面倒な遺産分割協議を避けられる
・関係の薄い兄弟や甥姪とのトラブルを防げる
・本当にお世話になった人に、確実に感謝の気持ちを届けられる
という 大きな安心を残された人に与えることができます。
だからこそ、**遺言書は、残された人への**「思いやりのプレゼント」”**とも言われています。
自分がいなくなった後も、大切な人が困らないように──。その備えが、あなた自身の安心にもつながります。
まずは、「自分が遺したい相手って誰だろう?」と考えることから始めてみてください。
その小さな一歩が、あなたの想いをきちんと伝える遺言書につながっていきます。
☑ 遺言書は、大切な想いを“確実にカタチにする”ためのもの。
一人で悩まずに、行政書士など専門家のサポートを上手に使いながら、あなたらしい備えを整えていきましょう。
無料相談・ご予約はこちらから クリックしたらどちらも飛べるように↓
【お問い合わせフォーム】または【お電話:045-232-4491】
横浜で相続や遺言のご相談なら、経験豊富な行政書士が丁寧に対応いたします。
未来の安心のために。
まずは一歩、踏み出してみませんか?